システム保守の引き継ぎで失敗しないための完全ガイド|スムーズな移行と注意点を解説

- 「毎月の保守費用が高すぎる」
- 「連絡してもレスポンスが遅い」
- 「簡単な修正でも見積もりが高額」
――このような不満を抱えながら、現在の保守会社との契約を続けていませんか?
あるいは、「来月で保守契約を終了させていただきます」と、保守会社から一方的に契約終了を告げられて途方に暮れていませんか?
企業がシステム保守の引き継ぎを検討する背景には、様々な理由があるかと思います。
- 保守会社側の都合による契約終了という、避けられない事情
保守会社の事業撤退、担当エンジニアの退職、採算が合わないという理由での契約打ち切りなど、自社ではコントロールできない理由で、急遽新しい保守先を探さなければならない状況に追い込まれることがあります。 - コスト面の問題
月額保守費用が当初の想定を大きく上回っていたり、ちょっとした修正でも都度高額な見積もりが提示されたりすることで、予算を圧迫していませんか?特に、システムの規模に対して保守費用が見合っていないと感じることはありませんか? - 対応品質の低下
問い合わせへの返答が遅い、障害発生時の対応が不十分、定期的な報告がないなど、サービスレベルが期待値を下回っている状況が続いていませんか?このような状況では、ビジネスへの影響も心配になるのも無理はありません。 - 技術力やノウハウの不足
システムが古くなってきたのに最新技術への対応ができない、セキュリティ対策が不十分、パフォーマンス改善の提案がないなど、保守会社の技術力に疑問を感じていませんか? - コミュニケーションの問題
担当者が頻繁に変わる、ビジネス要件を理解してくれない、提案が的外れなど、パートナーとしての信頼関係が築けていないと感じることはありませんか?
このような状況に心当たりがある場合、システム保守の引き継ぎは有効な選択肢となりえます。ただし、引き継ぎにはリスクも伴うため、慎重な準備と計画が不可欠です。本記事では、保守引き継ぎを成功させるためのポイントを、実際の事例を交えながら詳しく解説していきます。

目次
失敗しないためのシステム保守の引継ぎチェックリスト

この資料でわかること
こんな方におすすめです
- 現在の保守会社のサービスに不満を感じている方
- 保守会社の変更を検討しているが、何から始めればよいか分からない方
- 引継ぎ作業でトラブルを避けたい方
システム保守の引き継ぎで起こりがちな問題とリスク
システム保守の引き継ぎは、適切に行わないと想定外のトラブルに見舞われることがあります。ここでは、実際によく起こる問題とリスクについて、詳しく見ていきましょう。
ドキュメント不足による混乱
最も深刻な問題の一つが、ドキュメントの不足や不備です。
長年同じ会社が保守を担当していると、重要な情報が「担当者の頭の中」だけに存在していることがあります。システムの設計書、運用手順書、障害対応マニュアルなどが整備されていない、あるいは古い情報のまま更新されていないケースは珍しくありません。
このような状況で引き継ぎを行うと、新しい保守会社は手探り状態でシステムを理解しなければならず、初期段階でのトラブル対応に時間がかかったり、最悪の場合、障害を引き起こしてしまう可能性もあります。
技術的な断絶と知識の喪失
システムには、長年の運用で蓄積された暗黙知が存在します。
「このエラーが出たときは、実はこの部分をチェックする」「毎月第3火曜日にはこの処理が重くなる」といった、ドキュメント化されていない運用ノウハウは、引き継ぎ時に失われやすい情報です。
また、使用している技術スタックが古い場合、新しい保守会社のエンジニアがその技術に精通していない可能性もあります。例えば、レガシーな言語で書かれたシステムや、独自フレームワークを使用している場合、技術的なギャップが生じることがあります。
移行期間中のトラブル対応
引き継ぎ期間中は、責任の所在が曖昧になりやすい時期です。
「まだ正式に引き継いでいないから」と現行の保守会社が消極的になったり、「まだ完全に理解していないから」と新しい保守会社が及び腰になったりすることで、対応の遅れや品質低下が発生することがあります。
特に、この期間中に重大な障害が発生した場合、両社の連携不足により復旧が遅れ、ビジネスに大きな影響を与える可能性があります。
コスト面での想定外の出費
引き継ぎには、当初想定していなかった追加コストが発生することがあります。
コストの種類 | 内容 | 影響 |
|---|---|---|
調査費用 | システムの現状把握にかかる工数 | 初期費用の増大 |
ドキュメント作成費用 | 不足している文書の新規作成 | 予算オーバー |
並行稼働費用 | 新旧両社への支払いが重なる期間 | キャッシュフローへの影響 |
改修費用 | 引き継ぎを機に発覚した問題の修正 | 追加予算の必要性 |
これらのコストは、事前の見積もりに含まれていないことが多く、プロジェクト全体の予算を圧迫する要因となります。
これらの問題とリスクを理解した上で、適切な対策を講じることが、システム保守の引き継ぎを成功させる鍵となります。次章では、実際の失敗事例を通じて、これらのリスクがどのように顕在化するかを見ていきましょう。
失敗事例:システム保守の引き継ぎで陥りやすい落とし穴

ここでは、実際に起こった保守引き継ぎの失敗事例を3つご紹介します。これらの事例から、どのような点に注意すべきかを学んでいきましょう。
事例1:ドキュメントゼロからの引き継ぎ失敗
A社(製造業、従業員数約200名)のケース
A社は、10年以上同じ個人事業主に生産管理システムの保守を依頼していました。月額費用は安価でしたが、その開発者が突然体調を崩し、業務継続が困難になったため、急遽新しい保守会社を探すことになりました。
しかし、引き継ぎを始めてみると、システムに関するドキュメントが一切存在しないことが判明。設計書はもちろん、データベースの構造を示す資料すらありませんでした。前任者は「全て頭の中にある」という状態で、入院中のため詳しい話を聞くこともできません。
新しい保守会社は、システムのソースコードを解析することから始めましたが、独自の命名規則やコメントのない複雑なロジックに苦戦。結果として、引き継ぎに6ヶ月以上かかり、その間に発生した障害への対応も遅れ、生産ラインが一時停止する事態にまで発展しました。
最終的に、調査費用だけで300万円以上の追加コストが発生し、さらにシステムの一部を作り直す必要があったため、当初予算を大幅に超過することになりました。
事例2:技術スタックの違いによる混乱
B社(小売業、従業員数約150名)のケース
B社は、コスト削減を目的として、ECサイトの保守を別の会社に切り替えることにしました。現行の保守会社が使用していたのは独自開発のPHPフレームワークでしたが、新しい保守会社は最新の技術スタックを得意としており、レガシーシステムへの対応経験が乏しい状態でした。
引き継ぎ当初、新しい保守会社は「問題ない」と自信を見せていましたが、実際に作業を始めると技術的なギャップが次々と露呈。特に、独自フレームワークの仕様を理解するのに時間がかかり、簡単な修正作業でもミスが頻発しました。
ある日、商品価格の一括更新という定期作業でミスが発生し、全商品の価格が0円で表示される障害が発生。幸い早期に発見できましたが、その対応に追われている間に別の定期処理が滞り、在庫管理にも影響が出る事態となりました。
結局、新しい保守会社では対応しきれないと判断し、3ヶ月で契約を解除。元の保守会社に頭を下げて戻ることになりましたが、一度切った関係を修復するため、以前より月額費用が20%上昇することになりました。
事例3:コミュニケーション不足による長期化
C社(サービス業、従業員数約100名)のケース
C社は、顧客管理システムの保守を、より大手のシステム会社に切り替えることにしました。大手ならではの安心感と、提案された保守プランの充実度が決め手でした。
しかし、引き継ぎが始まると、組織の壁が問題となりました。新しい保守会社側は、営業担当、プロジェクトマネージャー、技術担当者など複数の窓口が存在し、C社からの質問や要望が適切に共有されないことが頻発。「それは営業に確認します」「技術担当から回答させます」といったやり取りが続き、簡単な確認事項でも回答に数日かかる状態でした。
また、引き継ぎ会議も形式的なものが多く、実務レベルでの詳細な情報共有が不十分でした。C社の担当者は「前の会社なら電話一本で解決していたのに」と不満を募らせます。
引き継ぎ期間は当初2ヶ月の予定でしたが、コミュニケーションの問題により4ヶ月以上に延長。その間、両社への支払いが重なり、月額保守費用が実質2倍になる期間が続きました。
さらに、引き継ぎ完了後も、新しい保守会社の対応スピードは改善されず、C社の業務効率は以前より低下。結果として、保守費用は下がったものの、社内の作業負担が増えるという本末転倒な結果となりました。
これらの失敗事例から分かるように、システム保守の引き継ぎは、技術面だけでなく、ドキュメント、コミュニケーション、組織体制など、多角的な視点での準備が必要です。次章では、これらの教訓を踏まえた成功事例をご紹介します。
成功事例:スムーズなシステム保守引き継ぎのポイント

失敗事例から学んだ教訓を活かし、実際に保守引き継ぎを成功させた企業の事例を3つご紹介します。これらの成功要因を参考に、自社の引き継ぎ計画を立ててみてください。
事例1:段階的な引き継ぎで実現した安定稼働
D社(物流業、従業員数約300名)のケース
D社は、倉庫管理システムの保守費用が年々上昇していることに悩んでいました。しかし、24時間365日稼働する物流センターのシステムだけに、引き継ぎには慎重にならざるを得ません。
そこで採用したのが、段階的な引き継ぎ方式でした。まず、新しい保守会社には「オブザーバー」として既存の保守作業に3ヶ月間同席してもらい、システムの特性や運用フローを学んでもらいました。この期間中、新旧両社でドキュメントの棚卸しと更新を共同で実施。曖昧だった仕様や、口頭でしか伝わっていなかった運用ルールを明文化しました。
次の段階では、比較的影響の小さい定期メンテナンス作業から順次移管。最初は旧保守会社の監督下で作業を行い、問題がないことを確認してから、徐々に新保守会社の裁量を増やしていきました。
また、引き継ぎ期間中は週次の定例会議を設け、D社、新旧保守会社の3者で進捗確認と課題共有を実施。小さな疑問点もその場で解決することで、認識のズレを防ぎました。
結果として、6ヶ月の引き継ぎ期間中、システム障害は一度も発生せず、スムーズな移行を実現。新保守会社の提案により、その後のシステム改善も進み、保守費用を30%削減しながら、サービス品質は向上するという理想的な結果となりました。
事例2:綿密な準備による短期間での移行成功
E社(金融業、従業員数約500名)のケース
E社は、基幹システムの保守会社を変更する際、事前準備に6ヶ月をかけました。一見すると長いように思えますが、この準備期間が短期間での移行成功の鍵となりました。
まず、社内にプロジェクトチームを立ち上げ、現行システムの棚卸し作業を実施。システム構成、使用技術、運用手順、過去の障害履歴など、あらゆる情報を整理し、引き継ぎ資料パッケージを作成しました。この資料は、新保守会社の選定時にも活用し、各社の技術力や対応能力を正確に評価することができました。
新保守会社が決定してからは、リハーサルを重視しました。本番環境と同等のテスト環境を用意し、定期作業、障害対応、緊急時対応など、様々なシナリオでの対応訓練を実施。この過程で発見された課題は、本番移行前にすべて解決しました。
また、E社は移行判定基準を明確に設定。「全ての定期作業が問題なく実施できること」「障害対応訓練で規定時間内に復旧できること」など、具体的な基準をクリアしてから本番移行を実施しました。
この綿密な準備により、実際の引き継ぎ期間はわずか1ヶ月で完了。移行後も安定稼働を続け、新保守会社の提案により、セキュリティ強化やパフォーマンス改善も実現しています。
事例3:積極的なコミュニケーションで実現した改善
F社(小売業、店舗数約50店)のケース
F社は、POSシステムと在庫管理システムの保守を新しい会社に切り替える際、コミュニケーション体制の構築を最重視しました。
引き継ぎ期間中は、定例会議に加えて、専用のチャットツールを導入。些細な疑問でも気軽に質問できる環境を整えました。新保守会社のエンジニアは、店舗にも足を運び、実際のシステム利用シーンを観察。現場の声を直接聞くことで、システムの本質的な理解を深めました。
また、F社は新保守会社に対して、改善提案を歓迎する姿勢を明確に示しました。「今までこうだったから」という固定観念を捨て、より良い方法があれば積極的に採用。この姿勢が新保守会社のモチベーションを高め、様々な改善提案が生まれました。
結果として、引き継ぎ完了後、システムの応答速度が50%向上、月次の定期作業時間が70%短縮されるなど、大幅な改善を実現。保守費用は前社とほぼ同額ながら、得られる価値は格段に向上しました。
これらの成功事例に共通しているのは、準備の重要性、段階的なアプローチ、コミュニケーションの重視です。次章では、これらの要素を踏まえた、具体的な引き継ぎステップをご紹介します。
システム保守を引き継ぐ際の具体的なステップ
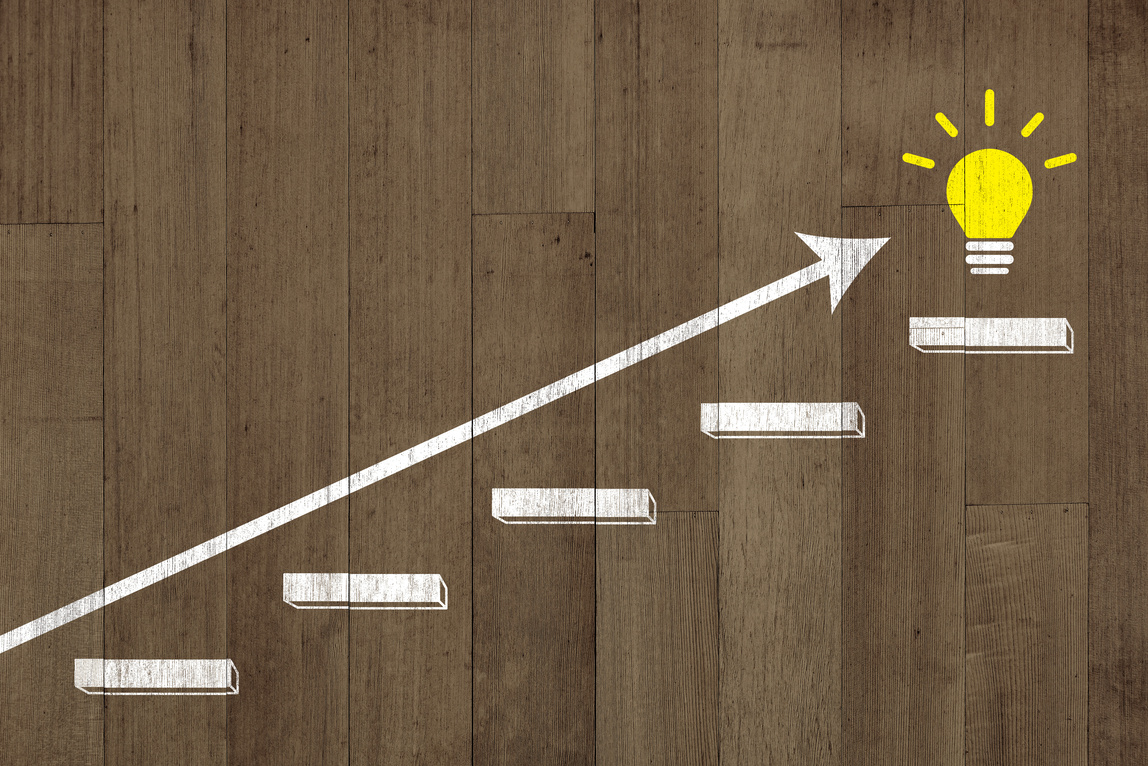
ここまでの事例を踏まえ、システム保守の引き継ぎを成功させるための具体的なステップを解説します。各ステップを着実に実行することで、リスクを最小化しながらスムーズな移行を実現できます。
現状調査と評価
まず最初に行うべきは、現状の正確な把握です。
システムの規模や複雑さ、使用技術、運用状況など、あらゆる角度から現状を調査します。特に以下の項目は必ず確認してください。
- システム構成:サーバー台数、ネットワーク構成、使用しているクラウドサービス
- 技術スタック:プログラミング言語、フレームワーク、データベース、ミドルウェア
- 運用状況:定期作業の頻度と内容、過去1年間の障害履歴、平均的な問い合わせ件数
- ドキュメント:設計書、運用手順書、障害対応マニュアルの有無と更新状況
- 契約内容:現在の保守範囲、SLA(サービスレベル合意)、費用の内訳
この調査結果を基に、引き継ぎの難易度とリスクを評価します。ドキュメントが不足している、技術が特殊である、運用が複雑であるなど、リスク要因を明確にすることで、適切な対策を立てることができます。
引き継ぎ計画の策定
現状調査の結果を踏まえ、詳細な引き継ぎ計画を策定します。
計画には、以下の要素を必ず含めてください。
計画項目 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
スケジュール | 引き継ぎ開始から完了までの詳細な工程 | バッファを十分に確保する |
体制 | 新旧保守会社と自社の役割分担 | 責任者を明確にする |
引き継ぎ範囲 | 段階的に移行する場合の優先順位 | リスクの低い部分から開始 |
判定基準 | 各段階の完了判定基準 | 定量的な基準を設定 |
リスク対策 | 想定されるリスクと対応策 | 最悪のケースも想定 |
特に重要なのは、段階的な移行計画です。一度にすべてを引き継ぐのではなく、影響の小さい部分から順次移行することで、リスクを分散できます。
ドキュメントの整備と確認
引き継ぎの成否を左右する重要な要素がドキュメントの整備です。
既存のドキュメントを確認し、不足している部分は引き継ぎ前に必ず作成します。最低限必要なドキュメントは以下の通りです。
- システム設計書:全体構成、機能一覧、データフロー
- インフラ構成図:ネットワーク図、サーバー構成、セキュリティ設定
- 運用手順書:定期作業手順、バックアップ手順、監視項目
- 障害対応手順書:よくある障害と対処法、エスカレーションフロー
- 環境情報:各種アカウント情報、ライセンス情報、契約情報
これらのドキュメントは、新保守会社と一緒にレビューを行い、不明点や改善点があれば引き継ぎ前に解決しておきます。
段階的な移行の実施
いよいよ実際の引き継ぎ作業です。成功のカギは段階的なアプローチにあります。
第1段階:観察期間(1〜2ヶ月) 新保守会社は既存の作業を観察し、システムと運用の理解を深めます。この期間中に疑問点を解消し、作業手順を習得します。
第2段階:共同作業期間(1〜2ヶ月) 新旧保守会社が共同で作業を行います。新保守会社が主体となり、旧保守会社がサポートする形で、徐々に責任を移行していきます。
第3段階:並行稼働期間(1ヶ月) 新保守会社が単独で作業を行いますが、旧保守会社もスタンバイ状態を維持。問題が発生した場合はすぐにサポートできる体制を整えます。
第4段階:完全移行 すべての判定基準をクリアしたら、正式に引き継ぎ完了となります。
引き継ぎ後のフォローアップ
引き継ぎが完了しても、すぐに安心してはいけません。継続的なフォローアップが重要です。
引き継ぎ完了後も、最低3ヶ月間は以下の活動を継続してください。
- 定期的なレビュー会議:月1回以上、サービス品質や課題を確認
- KPIモニタリング:応答時間、解決時間、稼働率などを継続的に監視
- 改善提案の検討:新保守会社からの提案を積極的に検討し、より良いシステム運用を目指す
- ドキュメントの更新:運用を通じて得られた知見を随時ドキュメントに反映
これらのステップを確実に実行することで、システム保守の引き継ぎを成功に導くことができます。次章では、より柔軟で効果的な保守体制を実現する、新しい選択肢についてご紹介します。
作業時間削減
システム化を通して時間を生み出し、ビジネスの加速をサポートします。
システム開発が可能に
秋霜堂のTechBandが提供する「システム開発部門」という新しい選択肢
ここまで、システム保守の引き継ぎについて詳しく解説してきましたが、実は保守の問題を根本的に解決する第3の選択肢があります。それが、秋霜堂株式会社が提供する「TechBand」サービスです。
一般的な受託開発との違い
従来の保守サービスと、TechBandの最大の違いは何でしょうか?
一般的な受託開発会社は、**「システムを開発して納品すること」**が目的です。保守契約を結んでいても、あくまで「外部の業者」として、決められた範囲の作業を行うだけ。お客様のビジネスを深く理解し、一緒に成長していくという視点は希薄になりがちです。
一方、TechBandは**「システム開発部門を提供する」**サービスです。つまり、お客様の会社に「システム開発部門ができた」かのように、内部組織として活動します。
比較項目 | 一般的な受託開発 | TechBand |
|---|---|---|
立ち位置 | 外部の委託先 | 内部のシステム開発部門 |
目的 | 依頼された作業の完了 | ビジネスの成功をサポート |
提案姿勢 | 受動的(依頼待ち) | 能動的(積極的な改善提案) |
ビジネス理解 | 表面的 | 深い理解と共感 |
コミュニケーション | 定例会議中心 | 日常的で密接な連携 |
費用の考え方 | 固定的 | 柔軟に調整可能 |
この違いは、実際の保守業務において大きな差となって現れます。
内部組織として機能するメリット
TechBandが「内部組織」として機能することで、どのようなメリットがあるのでしょうか?
1. ビジネスの深い理解に基づく提案 外部の保守会社は、システムの技術的な側面しか見ていないことが多いです。しかし、TechBandはお客様のビジネスモデル、業界特性、将来の展望まで理解した上で、本当に必要な改善提案を行います。
例えば、「このボタンの色を変えてほしい」という依頼に対して、一般的な保守会社は言われた通りに変更するだけ。でもTechBandなら、「なぜ変更したいのか」を深く理解し、「実はこういう機能を追加した方が、お客様の目的を達成できるのでは?」という本質的な提案ができます。
2. スピーディーな意思決定と実行 内部組織として活動するため、いちいち見積もりを取って、稟議を通して…という手間が大幅に削減されます。必要な改修や改善を、スピーディーに実行できるのです。
3. 継続的な改善の文化 単発の作業ではなく、継続的にシステムを改善していく。まさに社内のシステム開発部門と同じように、日々の小さな改善を積み重ねることで、システムの価値を高めていきます。
4. 知識とノウハウの蓄積 担当者が変わるたびに一から説明…ということがありません。TechBandは専属チームとして、お客様のシステムに関する知識とノウハウを確実に蓄積していきます。
柔軟な費用とリソース調整
「でも、システム開発部門を持つなんて、コストが心配…」
そんな不安も、TechBandなら解消できます。なぜなら、必要な時に必要な分だけリソースを調整できるからです。
フェーズに応じた最適なリソース配分
- 通常時:1〜2名の少人数体制で日常的な保守運用
- 機能追加時:3〜4名に増員して集中的に開発
- 大規模改修時:5名以上の体制で短期間で実装
- 安定期:最小限の体制に戻してコストを抑制
このように、プロジェクトのフェーズや業務量に応じて柔軟にリソースを調整することで、常に最適なコストパフォーマンスを実現します。
予算に応じた優先順位付け 限られた予算の中で最大の効果を出すため、TechBandは改善項目に優先順位を付けて提案します。「今月はこの機能改善を」「来月は性能改善を」というように、計画的な改善を進めることができます。
透明性の高い費用管理 何にどれだけの工数がかかったのか、どんな価値を生み出したのか。TechBandは定期的なレポートで、費用対効果を明確に示します。「保守費用が何に使われているか分からない」という不満とは無縁です。
実際のプロジェクトでも、この柔軟性が高く評価されています。先ほどご紹介した文書にあるように、MVP開発を2ヶ月・2名体制でスタートし、需要確認後に6〜8名に増員して本格開発を進めた事例もあります。
TechBandは、単なる保守会社の変更ではなく、システム運用の在り方そのものを変える新しい選択肢なのです。保守引き継ぎを成功させるためのチェックリストもご用意していますので、ぜひ御覧ください。
まとめ:システム保守の引き継ぎは秋霜堂にお任せください
ここまで、システム保守の引き継ぎについて、失敗事例から成功事例、具体的なステップまで詳しく解説してきました。
保守の引き継ぎを成功させるポイントをもう一度整理すると:
- 十分な準備期間を確保し、現状を正確に把握する
- ドキュメントの整備を怠らず、知識の継承を確実に行う
- 段階的な移行でリスクを最小化する
- 密接なコミュニケーションで認識のズレを防ぐ
- 継続的な改善を前提とした体制を構築する
しかし、これらを実践するのは決して簡単ではありません。特に、システム開発の経験が少ない企業様にとっては、何から手を付けていいか分からないというのが正直なところではないでしょうか?
秋霜堂株式会社のTechBandなら、そんな不安を解消できます。
なぜなら、私たちは単なる「保守会社」ではなく、お客様の「システム開発部門」として機能するからです。前任の保守会社からの引き継ぎはもちろん、ドキュメントがない状態からの立て直し、レガシーシステムの改善など、様々な困難な状況にも対応してきました。
実際に、ある企業様では「海外の開発会社が作った品質の悪いシステム」を引き継ぎ、データバックアップの仕組みを構築し、同時アクセスによるシステムダウンを解消。「まるで本当にシステム開発部門が誕生したよう」という評価をいただいています。
また、別の企業様では、前例のないSNSマーケティング支援システムの開発において、競合調査から収益シミュレーション、開発、リリース後の改善まで一貫してサポート。「ここまで寄り添ってくれる開発会社は初めてだ」とのお言葉をいただきました。
今、このようなお悩みを抱えていませんか?
- 現在の保守費用が高すぎて、もっと費用対効果の高い会社を探している
- 保守会社の対応が遅く、ビジネスのスピードについていけない
- システムの引き継ぎをしたいが、ドキュメントもなく、どこから始めればいいか分からない
- 単なる保守だけでなく、積極的な改善提案がほしい
- 社内にIT部門がないので、信頼できるパートナーがほしい
システム保守の引き継ぎは、企業の成長にとって重要な転換点です。
この機会を、単なる「保守会社の変更」で終わらせるのか、それとも「真のパートナーとの出会い」にするのか。その選択が、今後のビジネスの成長を大きく左右します。
秋霜堂株式会社は、最先端のソフトウェア技術を用いたWebシステムやAI開発に強みを持つエンジニア集団です。プロジェクトごとに専属チームを編成し、お客様にとって本当に価値のあるシステム開発サービスをご提供いたします。
次の一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか?
失敗しないためのシステム保守の引継ぎチェックリスト

この資料でわかること
こんな方におすすめです
- 現在の保守会社のサービスに不満を感じている方
- 保守会社の変更を検討しているが、何から始めればよいか分からない方
- 引継ぎ作業でトラブルを避けたい方
作業時間削減
システム化を通して時間を生み出し、ビジネスの加速をサポートします。
システム開発が可能に









