フルスクラッチ開発とは?他の開発手法との違いとメリット・デメリットを徹底解説

「自社の業務に完璧にフィットするシステムが欲しいけれど、どんな開発方法を選べばいいのかわからない」
このような悩みを抱えている企業の経営者や担当者の方は多いのではないでしょうか。市販のパッケージソフトでは物足りない、かといってゼロから作るのは大変そう...。そんな迷いの中で、よく耳にするのが「フルスクラッチ開発」という言葉です。
フルスクラッチ開発とは、既存のシステムやパッケージを使わず、まっさらな状態から完全オーダーメイドでシステムを構築する開発手法のことです。建築に例えるなら、建売住宅を購入するのではなく、土地選びから間取り設計まですべて自分たちの希望通りに注文住宅を建てるようなものです。
しかし、「フルスクラッチ開発は高い」「時間がかかる」といったイメージから、二の足を踏んでいる方も多いかもしれません。確かにデメリットもありますが、適切に進めれば、他の開発手法では実現できない大きなメリットを得ることができます。
本記事では、フルスクラッチ開発について、パッケージ導入やノーコード開発など他の手法と比較しながら、そのメリット・デメリットを詳しく解説します。さらに、実際の成功事例・失敗事例を交えながら、どのような場合にフルスクラッチ開発を選ぶべきか、成功させるためのポイントは何かをお伝えします。
システム開発の手法選びで迷っている方にとって、最適な判断をするための道しるべとなれば幸いです。

目次
失敗しないためのシステム開発の考え方と開発パートナー選定チェックリスト

この資料でわかること
こんな方におすすめです
- システム開発を検討しているが、失敗したくない
- 開発パートナーを選定しているが、選び方がわからない
- システム開発の失敗パターンを知っておきたい
フルスクラッチ開発とは?基本をわかりやすく解説

フルスクラッチ開発の定義
フルスクラッチ開発とは、既存のシステムやテンプレート、パッケージソフトを一切使わず、ゼロから完全オリジナルのシステムを開発する手法です。「スクラッチ」は英語で「ひっかき傷」や「ゼロから」という意味があり、まさに白紙の状態から始めることを表しています。
料理に例えるなら、レトルト食品や冷凍食品を使わず、素材選びから調理まですべて手作りで行うようなものです。手間はかかりますが、味付けや盛り付けまで、すべてを自分好みにカスタマイズできるのが最大の特徴です。
具体的にどのような開発なのか
フルスクラッチ開発では、以下のような工程をすべてオーダーメイドで進めていきます。
- 要件定義
お客様の業務内容や課題を詳しくヒアリングし、「どんなシステムが必要か」を明確にします。既存のパッケージに合わせるのではなく、業務に合わせてシステムを設計するため、この段階が特に重要になります。 - 設計
画面のレイアウトから、データの流れ、操作方法まで、すべてをお客様の要望に合わせて設計します。使いやすさや効率性を追求し、現場の声を反映させることができます。 - 開発
プログラマーが一行一行コードを書いて、システムを構築していきます。市販のソフトでは実現できない独自の機能も、技術的に可能な限り実装することができます。 - テスト・改善
完成したシステムが正しく動作するか、使いやすいかを確認し、必要に応じて修正を行います。お客様の要望に100%応えるまで、このプロセスを繰り返します。
どんな企業・プロジェクトに向いているか
フルスクラッチ開発が特に適しているのは、以下のようなケースです。
- 独自の業務フローがある企業
「うちの会社独特のやり方があって、市販のソフトでは対応できない」という場合、フルスクラッチ開発なら完全に業務に合わせたシステムを作ることができます。 - 競合他社と差別化したい企業
同じパッケージソフトを使っていては、競合他社と同じことしかできません。独自のシステムで、他社にはないサービスや効率性を実現したい場合に適しています。 - 将来的な拡張を見据えている企業
事業の成長に合わせてシステムも進化させたい場合、フルスクラッチなら自由に機能追加や改修が可能です。 - セキュリティを重視する企業
金融機関や個人情報を扱う企業など、高度なセキュリティが求められる場合、独自の基準でシステムを構築できるフルスクラッチ開発が選ばれることが多いです。
一方で、「標準的な機能で十分」「すぐに使い始めたい」「予算が限られている」という場合は、他の開発手法を検討する方が良いかもしれません。次章では、他の開発手法との違いを詳しく比較していきます。
フルスクラッチ開発と他の開発手法の比較
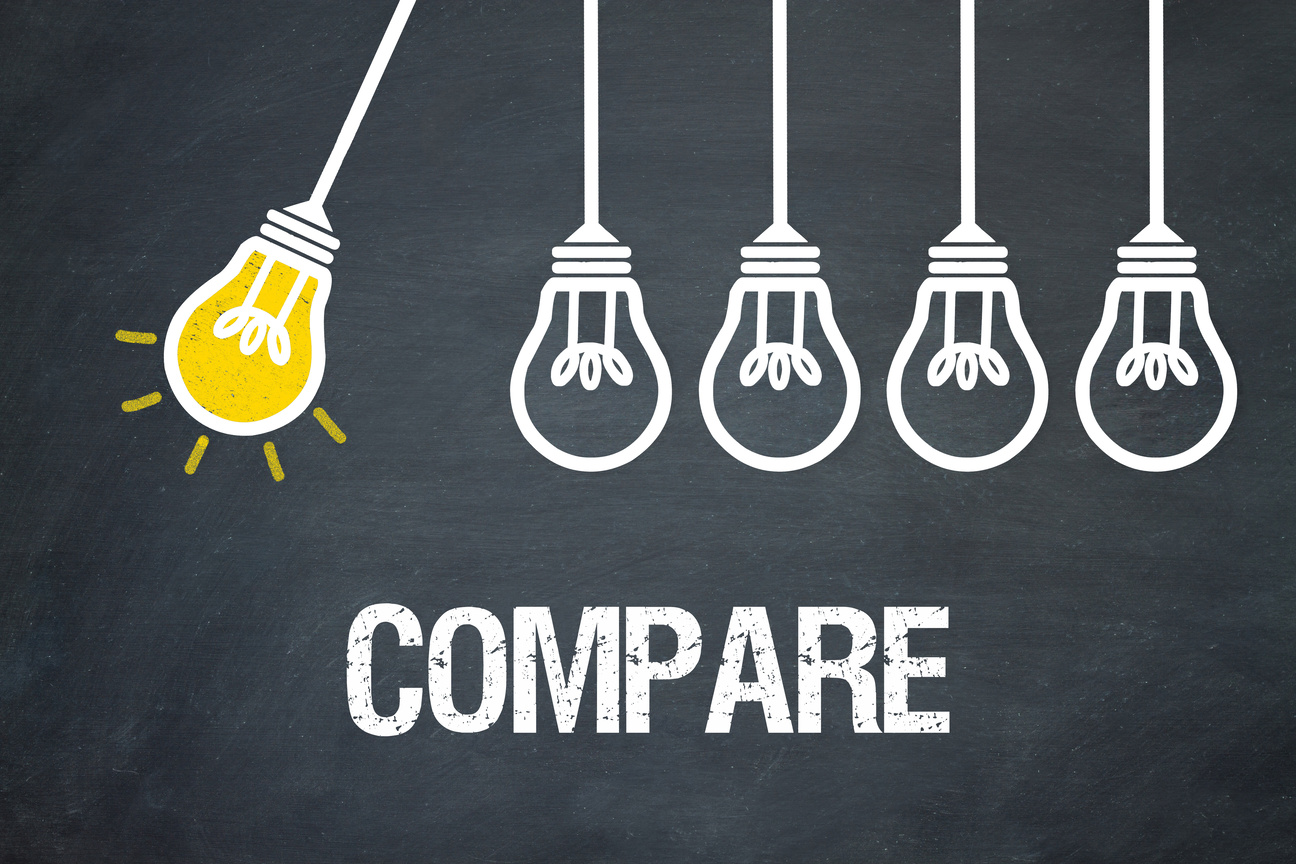
システム開発には、フルスクラッチ開発以外にもさまざまな手法があります。それぞれの特徴を理解することで、自社にとって最適な選択ができるようになります。ここでは、代表的な3つの手法とフルスクラッチ開発を比較していきます。
パッケージ導入との違い
パッケージ導入とは、すでに完成している市販のソフトウェアを購入して使用する方法です。会計ソフトや顧客管理システムなど、多くの企業で共通して使われる機能をまとめた製品が該当します。
特徴の比較
パッケージソフトは「既製品」、フルスクラッチは「オーダーメイド」という大きな違いがあります。洋服で例えるなら、パッケージは既製服、フルスクラッチはオーダースーツのような関係です。
パッケージソフトは、多くの企業で使えるよう汎用的に作られているため、すぐに導入できる反面、自社の業務に100%フィットすることは稀です。一方、フルスクラッチ開発なら、ボタンの配置から業務の流れまで、すべてを自社仕様にできます。
コスト面での違い
初期費用では、パッケージ導入が圧倒的に安くなります。パッケージソフトは開発費を多数のユーザーで分担するため、1社あたりの負担が軽くなるからです。フルスクラッチ開発は、開発費用をすべて1社で負担することになるため、初期投資は大きくなります。
ただし、長期的な視点で見ると話は変わってきます。パッケージソフトは毎年のライセンス料や、カスタマイズのたびに追加費用がかかることが多く、5年、10年と使い続けると、トータルコストが膨らむケースもあります。
カスタマイズ性の違い
パッケージソフトのカスタマイズには限界があります。基本機能は変更できず、追加できる機能も制限されることがほとんどです。無理にカスタマイズしようとすると、バージョンアップのたびに不具合が発生するリスクもあります。
フルスクラッチ開発なら、技術的に可能な限り、どんな機能でも実装できます。業務の変化に合わせて柔軟に改修することも可能で、自社の成長とともにシステムも進化させられます。
ノーコード・ローコード開発との違い
最近注目されているのが、プログラミングの知識がなくても(または少なくても)システムを作れる「ノーコード・ローコード開発」です。
開発スピードの違い
ノーコード・ローコード開発の最大の魅力は、そのスピード感です。あらかじめ用意された部品を組み合わせるだけで、数日から数週間で簡単なシステムが完成します。
フルスクラッチ開発は、すべてを一から作るため、どうしても時間がかかります。小規模なシステムでも数ヶ月、大規模なものだと1年以上かかることもあります。
拡張性・柔軟性の違い
ノーコード・ローコードツールは、用意された機能の範囲内でしかシステムを作れません。「この機能とこの機能を組み合わせたい」と思っても、ツールが対応していなければ実現不可能です。
フルスクラッチ開発なら、技術的な制約はあるものの、基本的にはどんな要望にも対応できます。複雑な計算処理や、他システムとの連携なども自在に実装可能です。
技術的な制約の違い
ノーコード・ローコードツールは、処理速度やデータ容量に制限があることが多く、大規模なシステムや高速処理が必要な業務には向きません。また、ツールの提供が終了すると、システム自体が使えなくなるリスクもあります。
フルスクラッチ開発は、サーバーの性能や設計次第で、どんな規模のシステムにも対応できます。自社でソースコードを保有するため、開発会社が変わっても継続して使用できる安心感もあります。
既存システムの改修との違い
すでに使っているシステムを改修する方法と、フルスクラッチで新規開発する方法の違いも重要なポイントです。
新規開発と改修の違い
既存システムの改修は、今あるものをベースに機能を追加・変更する方法です。家で例えるなら、リフォームやリノベーションにあたります。使い慣れた部分を残しながら、問題のある箇所だけを改善できるメリットがあります。
しかし、古いシステムの場合、土台となる技術が時代遅れになっていることがあります。無理に改修を重ねると、継ぎ接ぎだらけの複雑なシステムになり、不具合の温床となることも少なくありません。
それぞれのメリット・デメリット
既存システムの改修は、費用を抑えられる、使い慣れた操作を維持できる、データ移行が簡単といったメリットがあります。一方で、根本的な問題は解決できない、改修を重ねるほど複雑になる、最新技術を導入しづらいといったデメリットもあります。
フルスクラッチ開発なら、最新の技術で最適な設計ができ、今後10年、20年使い続けられる基盤を作れます。ただし、初期投資が大きく、ユーザーの教育が必要になるなどの課題もあります。
どちらを選ぶかは、現在のシステムの状態、予算、将来の事業計画などを総合的に判断する必要があります。
フルスクラッチ開発のメリット
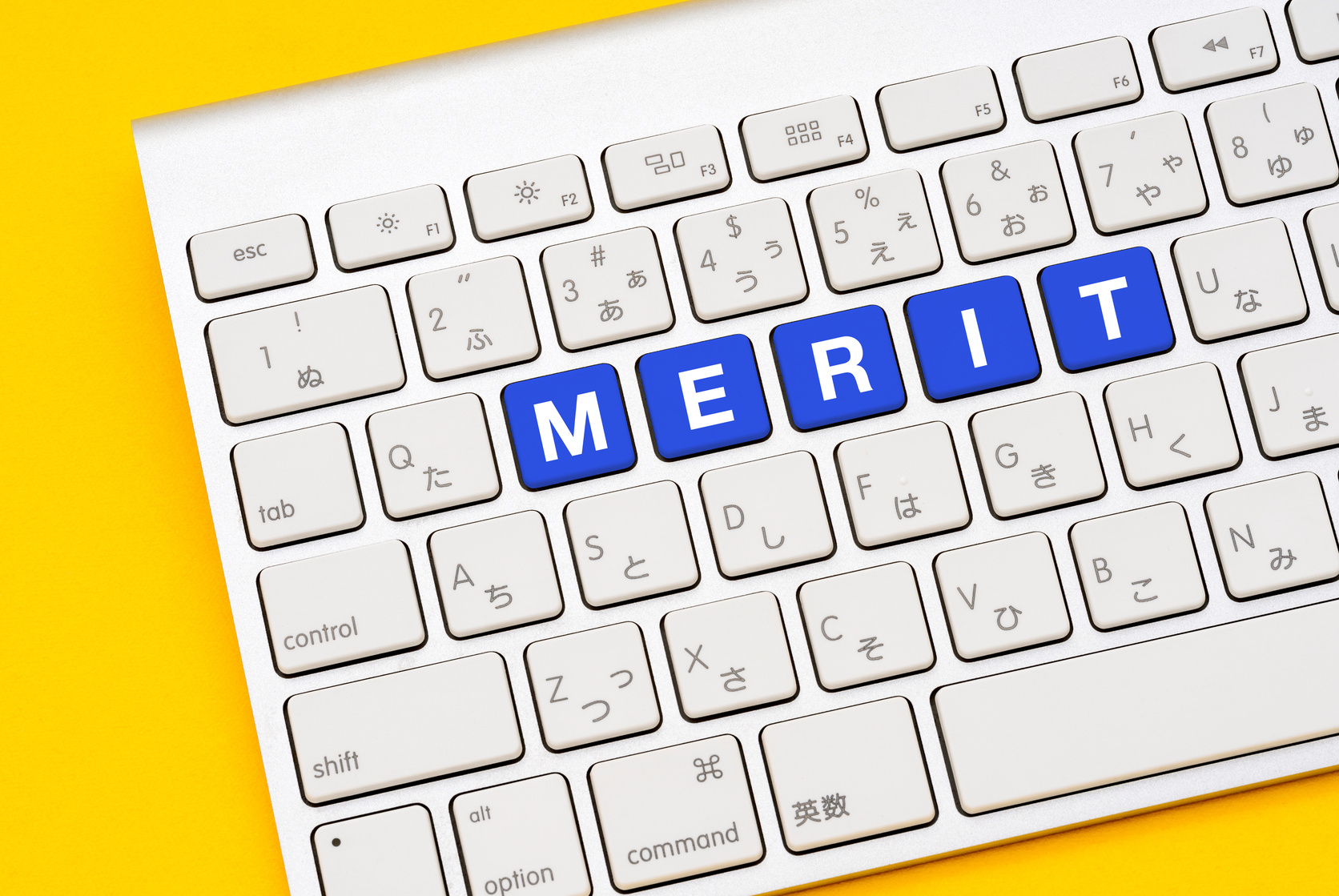
フルスクラッチ開発には、他の開発手法では得られない大きなメリットがあります。ここでは、実際の開発現場での経験を踏まえて、4つの主要なメリットを詳しく解説します。
完全オーダーメイドで理想のシステムが作れる
フルスクラッチ開発の最大のメリットは、自社の業務に100%フィットするシステムを作れることです。
例えば、ある広告制作会社では、動画の確認作業に独自のワークフローがありました。市販のツールでは「動画をアップロードして、コメントを付ける」という基本機能しかありませんでしたが、実際の業務では「特定の秒数でコメントを付けたい」「複数の関係者の承認フローを管理したい」「過去の修正履歴を一覧で見たい」など、細かな要望がありました。
フルスクラッチ開発により、これらすべての要望を実現したシステムを構築。その結果、確認作業にかかる時間が従来の半分以下になり、「もう前のやり方には戻れない」という声が上がるほど、業務効率が向上しました。
画面のデザインも自由自在です。自社のコーポレートカラーに合わせたり、普段使い慣れているツールと似た操作感にしたりすることで、社員がストレスなく使えるシステムになります。ボタンの配置一つとっても、「よく使う機能は大きく、目立つ場所に」といった工夫ができるのは、フルスクラッチならではの利点です。
拡張性・保守性が高い
ビジネスは常に変化し、成長していきます。フルスクラッチ開発なら、その変化に柔軟に対応できる拡張性の高いシステムを構築できます。
最初は社内利用のみを想定していたシステムでも、将来的な外部販売を見据えた設計にしておけば、新たなビジネスチャンスにもつながります。実際に、社内の業務効率化のために開発したシステムが評判を呼び、同業他社から「うちでも使いたい」という問い合わせが来て、新しい収益源になったケースもあります。
また、自社でソースコード(プログラムの設計図)を保有できるため、開発会社を変更しても継続して保守・改修が可能です。パッケージソフトのように、ベンダー(販売元)の都合でサポートが終了する心配もありません。
技術的な面でも、最新の開発手法を採用できるため、保守性の高いシステムを作れます。例えば、マイクロサービスアーキテクチャという設計手法を使えば、機能ごとに独立したモジュールとして開発でき、一部を改修しても他の部分に影響が出にくい構造にできます。
セキュリティを自社基準で設計できる
情報セキュリティは、現代のビジネスにおいて最重要課題の一つです。フルスクラッチ開発なら、自社のセキュリティポリシーに完全に準拠したシステムを構築できます。
パッケージソフトやクラウドサービスでは、データがどこに保存されているか、どのようなセキュリティ対策が取られているかがブラックボックスになりがちです。一方、フルスクラッチ開発では、データの保存場所から暗号化の方式、アクセス権限の設定まで、すべてを自社でコントロールできます。
金融機関や医療機関など、特に高いセキュリティレベルが求められる業界では、このメリットは非常に大きな意味を持ちます。監査への対応も、システムの仕組みを完全に把握しているため、スムーズに行えます。
また、不正アクセスの検知システムや、操作ログの詳細な記録など、自社特有のセキュリティ要件も自由に実装できます。万が一の情報漏洩リスクを最小限に抑えることができるのです。
競合他社との差別化が図れる
ビジネスにおいて、競合他社との差別化は生き残りをかけた重要な戦略です。フルスクラッチ開発は、その差別化を技術面から強力にサポートします。
同じ業界の企業が同じパッケージソフトを使っていれば、提供できるサービスも似通ってしまいます。しかし、独自のシステムがあれば、他社にはない付加価値を顧客に提供できます。
例えば、ある小売業の企業では、フルスクラッチで開発した教育用アプリにより、新人アルバイトの研修期間を従来の半分に短縮しました。これにより、人材不足の時代でも素早く戦力化でき、顧客サービスの質を維持。「あの店は新人でもしっかりしている」という評判につながり、競合店との明確な差別化要因となりました。
また、独自システムの存在自体が、企業のイノベーション力をアピールする材料にもなります。「最新技術を活用している先進的な企業」というブランドイメージの構築にも貢献するのです。
これらのメリットを最大限に活かすためには、適切な開発パートナーの選定と、綿密な計画が不可欠です。次章では、フルスクラッチ開発のデメリットと、それを克服する方法について詳しく見ていきましょう。
フルスクラッチ開発のデメリットと対策

フルスクラッチ開発には大きなメリットがある一方で、デメリットも存在します。しかし、これらのデメリットは適切な対策を取ることで、十分に克服可能です。ここでは、主なデメリットとその具体的な対策方法を解説します。
初期費用が高い → 段階的な開発で対応
フルスクラッチ開発の最大のハードルは、やはり初期費用の高さです。すべてをゼロから作るため、開発にかかる人件費が大きくなり、数百万円から数千万円の投資が必要になることもあります。
しかし、この課題は「段階的な開発」で解決できます。最初からすべての機能を実装するのではなく、最も重要な機能から順番に開発していく方法です。
MVP(Minimum Viable Product)開発という選択肢
まずは最小限の機能で動くシステム(MVP)を2〜3ヶ月で開発し、実際に使いながら本当に必要な機能を見極めていきます。この方法なら、初期投資を200〜300万円程度に抑えることも可能です。
例えば、SNSマーケティング支援システムの開発事例では、最初の2ヶ月でMVPを開発し、その後、利用状況を見ながら機能を追加していきました。結果的に、無駄な機能を作ることなく、本当に必要な機能だけに投資を集中できました。
費用対効果を見える化する
開発前に収益シミュレーションを行い、システム導入による業務効率化や売上増加の効果を数値化することも重要です。「月間100時間の作業時間削減 = 人件費換算で月50万円の削減」といった具体的な数字があれば、投資判断もしやすくなります。
開発期間が長い → アジャイル開発で短縮
フルスクラッチ開発は、一般的に6ヶ月から1年以上の開発期間が必要とされます。その間にビジネス環境が変わってしまうリスクもあります。
この問題に対しては、「アジャイル開発」という手法が有効です。
アジャイル開発とは
従来の開発手法では、最初にすべての仕様を決めてから開発を始めていました。しかしアジャイル開発では、2週間程度の短いサイクルで「開発→確認→改善」を繰り返します。
これにより、以下のようなメリットが得られます:
- 早い段階で動くシステムを確認できる
- 途中で要望が変わっても柔軟に対応できる
- 問題を早期に発見し、修正コストを抑えられる
並行作業で期間短縮
設計と開発を並行して進めることで、全体の期間を短縮することも可能です。例えば、画面デザインを確定させている間に、データベースの設計を進めるといった工夫により、6ヶ月かかる開発を4ヶ月に短縮できることもあります。
開発会社選びが難しい → 選定のポイント
フルスクラッチ開発の成否は、開発会社の技術力とコミュニケーション能力に大きく左右されます。しかし、どの会社を選べばよいか判断するのは簡単ではありません。
開発会社選定の5つのポイント
- 技術力の確認
過去の開発実績を詳しく確認し、自社と似た規模・業界での開発経験があるかチェックします。 - コミュニケーション体制
定期的な打ち合わせの頻度や、緊急時の連絡体制について事前に確認します。週1回の定例会議に加え、チャットでの日常的なやり取りができる会社が理想的です。 - 開発手法の確認
アジャイル開発に対応しているか、開発途中での仕様変更にどの程度柔軟に対応できるかを確認します。 - 見積もりの透明性
「一式○○万円」ではなく、機能ごとに詳細な見積もりを出してくれる会社を選びましょう。追加費用が発生する条件も明確にしておくことが重要です。 - 保守・運用体制
開発後のサポート体制も重要です。24時間対応が必要か、平日のみで十分かなど、自社の要望に合った体制を持つ会社を選びます。
保守・運用の必要性 → 適切なサポート体制
システムは作って終わりではありません。日々の運用や、定期的なメンテナンスが必要になります。
内製化か外注かの選択
保守・運用には大きく2つの選択肢があります:
- 社内にIT部門を作って内製化する
- 開発会社に継続的にサポートしてもらう
多くの中小企業では、専門のIT人材を雇用するのは現実的ではないため、開発会社との保守契約を結ぶケースが一般的です。月額10〜50万円程度で、以下のようなサポートを受けられます:
- システムの監視と障害対応
- セキュリティアップデート
- 軽微な改修や機能追加
- 利用者からの問い合わせ対応
「システム開発部門」という新しい選択肢
最近では、単なる保守契約ではなく、「システム開発部門」として継続的に伴走してくれるサービスも登場しています。これなら、社内にIT部門を持つのと同じような安心感を得られます。
これらの対策を適切に実施することで、フルスクラッチ開発のデメリットを最小限に抑え、メリットを最大限に活かすことができます。次章では、実際の成功事例を見ていきましょう。
失敗しないためのシステム開発の考え方と開発パートナー選定チェックリスト

この資料でわかること
こんな方におすすめです
- システム開発を検討しているが、失敗したくない
- 開発パートナーを選定しているが、選び方がわからない
- システム開発の失敗パターンを知っておきたい
フルスクラッチ開発の成功事例

実際にフルスクラッチ開発を選択し、大きな成果を上げた事例をご紹介します。この事例から、なぜフルスクラッチを選んだのか、どのような成果が得られたのかを具体的に見ていきましょう。
動画校正システムの新規開発事例
背景と課題
ある芸能・広告業界の企業(従業員50名)では、動画制作の校正作業に大きな課題を抱えていました。クライアントから修正指示を受ける際、メールやチャットでのやり取りだけでは、「動画の何分何秒の部分」という指示が曖昧になりがちで、認識のズレから手戻りが頻発していました。
市販の動画共有ツールも検討しましたが、以下の理由で自社のニーズに合いませんでした:
- タイムコード(秒単位)でのコメント機能がない
- 複数の関係者の承認フローを管理できない
- 過去の修正履歴を体系的に管理できない
- デザイン会社らしい洗練されたUIではない
なぜフルスクラッチを選んだのか
同社がフルスクラッチ開発を選択した理由は3つありました。
1. 業界特有のワークフローへの完全対応
広告業界では、クライアント、代理店、制作会社など、多くの関係者が関わります。それぞれの確認・承認プロセスを正確に管理する必要があり、汎用的なツールでは対応が困難でした。フルスクラッチなら、この複雑なワークフローを完全にシステム化できると判断しました。
2. 将来的なビジネス展開の可能性
「社内ツールとして成功すれば、同業他社にも販売できるのではないか」という構想がありました。フルスクラッチ開発なら、最初から外販を見据えた設計が可能です。
3. デザイン会社としてのこだわり
クリエイティブを扱う企業として、使用するツールのデザインにもこだわりたいという想いがありました。フルスクラッチなら、自社のブランドイメージに合った、美しく使いやすいインターフェースを実現できます。
開発プロセスと工夫
開発は6ヶ月間、エンジニア1〜2名の少数精鋭チームで進められました。
アジャイル開発での高速改善サイクル
週1回の定例ミーティングに加え、Slackでリアルタイムにコミュニケーションを取りながら開発を進めました。2週間ごとに実際に動作するプロトタイプを確認し、実際に使ってみて気づいた改善点をすぐに反映。この高速サイクルにより、使い勝手の良いシステムに仕上がりました。
現場の声を徹底的に反映
開発チームは実際の制作現場に入り込み、ディレクターやデザイナーの作業を観察。「ここでいつも時間がかかる」「この操作がストレス」といった生の声を集め、一つひとつ解決していきました。
例えば、「動画を見ながらコメントを書きたいが、一時停止すると画面が暗くなって見づらい」という意見から、一時停止時も明るさを保つ機能を実装。細かな配慮が、現場の満足度を大きく向上させました。
得られた成果
フルスクラッチ開発により、以下のような具体的な成果が得られました。
業務効率の大幅改善
- 動画1本あたりの校正にかかる時間が平均50%削減
- 修正の手戻り率が80%減少
- クライアントからの「修正指示がわかりやすくなった」という評価
社内の評価
導入後、社内からは「もう前のやり方には戻れない」という声が続出。特に以下の点が高く評価されました:
- 直感的な操作で、新人でもすぐに使いこなせる
- 過去の修正履歴が一目でわかり、なぜその修正が入ったかを把握できる
- 美しいUIで、クライアントに見せても恥ずかしくない
新たなビジネスチャンスの創出
当初の構想通り、このシステムは同業他社からも注目を集めました。「うちでも使いたい」という問い合わせが相次ぎ、SaaSとしての外販を検討する段階に入っています。社内ツールとして始まったプロジェクトが、新たな収益源になる可能性を秘めています。
投資対効果
開発費用は300〜500万円でしたが、業務効率化による人件費削減効果は月額約100万円と試算されています。わずか5ヶ月で投資を回収でき、その後は純粋な利益につながっています。さらに、外販による収益も期待でき、投資対効果は予想を大きく上回りました。
この成功事例が示すように、自社の業務に特化したシステムをフルスクラッチで開発することは、単なる効率化を超えて、新たなビジネスチャンスを生み出す可能性を秘めています。次章では、逆に失敗してしまった事例から、何を学ぶべきかを見ていきましょう。
フルスクラッチ開発の失敗事例から学ぶ

成功事例だけでなく、失敗事例から学ぶことも重要です。ここでは、実際に起きた失敗事例を通じて、フルスクラッチ開発で陥りやすい落とし穴と、それを回避する方法を解説します。
品質管理システムの失敗事例
背景と初期の決定
あるアパレル企業(従業員40名、海外工場作業員約1,700名)は、複数の海外工場での品質のバラつきを解消するため、品質管理システムの導入を決定しました。
システム開発の経験がなかった同社は、コストを最優先に考え、「一番安い見積もりを出した海外の開発会社」に発注しました。見積もり金額は国内の開発会社の3分の1という魅力的な価格でした。
失敗の原因分析
しかし、完成したシステムは「大失敗」と言わざるを得ない品質でした。具体的な問題と、その原因を分析してみましょう。
1. コミュニケーション不足による仕様の誤解
最大の問題は、言語の壁と文化の違いによるコミュニケーション不足でした。
- 日本語の微妙なニュアンスが伝わらず、要件が正確に理解されていなかった
- 時差により、質問への回答に1日以上かかることが常態化
- 「たぶん大丈夫だろう」という憶測で開発が進められた
結果として、「工場の作業員が同時にアクセスするとシステムがダウンする」という致命的な問題が発生。1,700名の作業員が使うことを想定していなかったのです。
2. 技術力不足と古い開発手法
安さを売りにしていた開発会社は、最新技術への投資を怠っていました。
- 10年以上前の古い技術で開発されていた
- データベースの設計が非効率で、読み込みに数分かかる
- なんとバックアップ機能すら実装されていなかった
3. ドキュメント不足による保守不能状態
開発会社は納品を急ぐあまり、以下の重要なドキュメントを作成していませんでした。
- システムの設計書
- プログラムの仕様書
- 操作マニュアル
これにより、「どこをどう直せばいいかわからない」という状況に陥り、改修すらできない状態になってしまいました。
4. 責任の所在が不明確
契約書の内容が曖昧で、問題が発生しても「仕様通りに作った」の一点張り。品質保証や瑕疵担保責任についての取り決めがなく、泣き寝入りするしかありませんでした。
失敗を防ぐためのポイント
この失敗事例から学べる、重要なポイントを整理します。
1. 価格だけで選ばない
「安物買いの銭失い」という言葉通り、初期費用の安さだけで選ぶと、結果的に高くつくことがあります。この事例では、作り直しの費用を含めると、最初から国内の信頼できる会社に頼んだ方が安く済んだはずです。
開発会社を選ぶ際は、以下の観点で総合的に判断しましょう:
- 技術力と実績
- コミュニケーション体制
- アフターサポート
- 品質保証の内容
2. 段階的な確認プロセスを設ける
一気に全部作って「完成しました」では、問題に気づいたときには手遅れです。以下のような段階的な確認が重要です:
- 要件定義の段階で、認識の齟齬がないか入念に確認
- プロトタイプの段階で、実際に使ってみて問題がないか検証
- 段階的にリリースし、問題を早期に発見・修正
3. 品質基準を明確にする
「ちゃんと動くシステム」では基準として曖昧すぎます。以下のような具体的な基準を設定し、契約書に明記することが重要です:
- 同時接続ユーザー数と応答速度の基準
- データのバックアップ頻度と復旧手順
- セキュリティ要件とテスト方法
- 納品されるドキュメントの種類と内容
4. 将来の保守・拡張を見据えた開発
システムは作って終わりではありません。最初から以下の点を考慮しておくことが大切です:
- 最新技術を使い、将来的な拡張に対応できる設計
- 十分なドキュメントの作成
- ソースコードの可読性と保守性
- 開発会社との長期的な関係構築
失敗からの復活
この企業は結局、国内の開発会社に依頼してシステムを改修することになりました。4ヶ月かけてインフラを刷新し、さらに6ヶ月かけてシステムを改善。最終的には、以下のような成果を得ることができました:
- 画面表示が数秒に短縮
- 同時接続での障害がゼロに
- 適切なバックアップ体制の確立
- 継続的な改善が可能な体制の構築
失敗を経験したからこそ、「本当に必要なもの」が明確になり、2度目の開発では的確な要件定義ができたという面もあります。ただし、最初から適切な選択をしていれば、時間とコストの無駄は避けられたはずです。
この事例が示すように、フルスクラッチ開発の成功には、適切なパートナー選びと、綿密な計画・管理が不可欠です。次章では、新しい選択肢として注目される「システム開発部門を提供する」サービスについて詳しく見ていきましょう。
TechBandが提供する「システム開発部門」という新しい選択肢
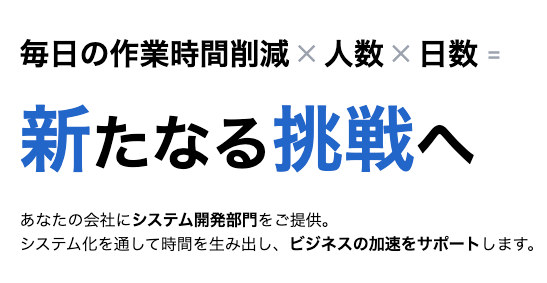
フルスクラッチ開発を成功させるには、単に「システムを作って納品する」だけでは不十分です。ここでは、秋霜堂が提供する「TechBand」という、従来の受託開発とは一線を画す新しいサービスについてご紹介します。
一般的な受託開発との違い
従来の受託開発とTechBandの最大の違いは、その立ち位置にあります。
一般的な受託開発の場合
通常の受託開発会社は「外部の業者」として、依頼されたシステムを開発し、納品することが目的です。建築に例えるなら、「家を建てて引き渡したら終わり」という関係性です。
このやり方には以下のような課題があります:
- 開発会社は御社のビジネスを深く理解しないまま開発を進める
- 納品後のサポートは「保守契約」という別料金
- ビジネスの変化に合わせた改善提案は期待できない
- トラブルが起きても「仕様通りです」で済まされることがある
TechBandの「システム開発部門」という考え方
TechBandは、御社の「システム開発部門」として、内部組織のように活動します。これは「家を建てる大工さん」ではなく、「一緒に住む家族」のような存在と言えるでしょう。
具体的には以下のような違いがあります:
- 御社のビジネスを深く理解し、一緒に成長を目指す
- システム開発だけでなく、業務改善の提案も積極的に行う
- 定期的なミーティングで、常に最新のビジネス状況を共有
- 「どうすれば御社のビジネスが成功するか」を第一に考える
内部組織として伴走するメリット
TechBandが「システム開発部門」として機能することで、以下のような大きなメリットが生まれます。
1. ビジネス理解の深さが違う
外部の開発会社は、どうしても表面的な理解に留まりがちです。しかし、内部組織として活動するTechBandは、御社のビジネスモデル、企業文化、将来のビジョンまで深く理解します。
実際のお客様からは、「まるで本当にシステム開発部門が誕生したよう」という声をいただいています。社内会議にも参加し、経営課題を共有しながら、最適なシステム戦略を一緒に考えていきます。
2. スピード感のある対応
外部業者の場合、「見積もりを取って、稟議を通して、発注して...」という手続きに時間がかかります。しかし、内部組織なら「この機能が必要だ」と思ったら、すぐに開発に着手できます。
アパレル企業の事例では、繁忙期前に緊急でシステム改修が必要になった際、通常なら1ヶ月かかる手続きを経ずに、即座に対応を開始。繁忙期に間に合わせることができました。
3. 継続的な改善提案
納品して終わりではなく、常に「もっと良くできないか」を考え続けます。日々の業務を観察し、「ここを自動化すれば、月20時間の削減になります」といった具体的な改善提案を行います。
小売業の教育アプリ開発事例では、初期開発後も現場の声を聞き続け、継続的に機能改善を実施。結果的に、新人教育期間を当初の目標以上に短縮することに成功しました。
柔軟な費用・リソース調整
TechBandの大きな特徴の一つが、プロジェクトの状況に応じた柔軟なリソース調整です。
フェーズに応じた最適なチーム編成
システム開発は、フェーズによって必要な人員が大きく変わります:
- 要件定義フェーズ:1〜2名の経験豊富なエンジニア
- 開発フェーズ:3〜6名の開発チーム
- 運用フェーズ:1〜2名の保守メンバー
一般的な受託開発では、契約で人数が固定されることが多く、無駄なコストが発生しがちです。TechBandなら、必要な時に必要な人数だけアサインすることで、コストを最適化できます。
成果に応じた投資判断
例えば、MVPを2ヶ月・200万円で開発し、成果を確認してから本格投資を判断することも可能です。「思ったような効果が出ない」場合は、そこで一旦ストップすることもできます。リスクを最小限に抑えながら、確実に成果を出していくアプローチです。
フルスクラッチ開発における強み
TechBandは、特にフルスクラッチ開発において、その真価を発揮します。
1. 長期的な視点での設計
単発のプロジェクトとしてではなく、御社の成長を見据えた設計を行います。「3年後にはこんな機能が必要になるだろう」という予測のもと、拡張性の高い手法を採用します。
2. 技術選定の最適化
最新技術を追いかけるだけでなく、御社のビジネスと技術レベルに最適な選択を行います。「枯れた技術で安定性重視」か「最新技術でイノベーション重視」か、一緒に議論しながら決定します。
3. 知識の蓄積と継承
開発したシステムの知識が社内に蓄積されていきます。ドキュメントの整備はもちろん、定期的な勉強会で社内メンバーへの知識移転も行います。将来的に内製化を目指す場合も、スムーズな移行が可能です。
TechBandは、単なる開発会社ではなく、御社のビジネスパートナーとして、共に成長していくことを目指しています。次章では、フルスクラッチ開発を成功させるための具体的なポイントをまとめていきます。
フルスクラッチ開発を成功させるための5つのポイント

ここまで、フルスクラッチ開発のメリット・デメリット、成功事例・失敗事例を見てきました。これらの経験から導き出された、フルスクラッチ開発を成功させるための重要なポイントを5つにまとめてご紹介します。
1. 要件定義の重要性
フルスクラッチ開発の成否は、要件定義の段階でほぼ決まると言っても過言ではありません。
なぜ要件定義が重要なのか
建築に例えると、要件定義は「設計図」を作る作業です。設計図が曖昧だと、完成した家が想像と違うものになってしまいます。システム開発でも同じで、最初の段階で「何を作るか」を明確にしておかないと、後から大きな手戻りが発生します。
要件定義を成功させるコツ
- 現場の声を徹底的に聞く:経営者の理想だけでなく、実際にシステムを使う現場スタッフの意見を重視する
- 具体的なシナリオで考える:「こんな時にこう使いたい」という具体的な利用シーンを想定する
- 優先順位を明確にする:「絶対必要」「あったら嬉しい」「将来的に欲しい」の3段階で整理する
- 図や画面イメージを活用:言葉だけでなく、視覚的に共有することで認識のズレを防ぐ
2. 適切な開発手法の選択
プロジェクトの性質に応じて、最適な開発手法を選ぶことが重要です。
ウォーターフォール vs アジャイル
従来のウォーターフォール開発は、最初にすべてを決めて順番に進める方法です。要件が明確で変更が少ない場合に適しています。
一方、アジャイル開発は、小さく作って改善を繰り返す方法です。要件が曖昧だったり、使いながら改善したい場合に適しています。フルスクラッチ開発では、アジャイル開発を選択するケースが増えています。
ハイブリッドアプローチ
実際には、両方の良いところを組み合わせることも可能です。例えば、基本設計はウォーターフォールでしっかり固め、詳細な機能はアジャイルで柔軟に開発するという方法です。
3. コミュニケーションの密度
開発会社との密なコミュニケーションは、成功の必須条件です。
定期的な進捗確認
週1回の定例会議を設定し、以下の点を確認します:
- 今週の進捗と来週の予定
- 課題や懸念事項の共有
- 仕様の確認や変更の相談
日常的なやり取り
定例会議だけでなく、SlackやChatworkなどのチャットツールで日常的にコミュニケーションを取ることも重要です。「ちょっとした疑問」をすぐに解決できる環境が、スムーズな開発につながります。
透明性の確保
開発の進捗状況を可視化し、「今どこまでできているか」「いつ完成予定か」を常に把握できるようにします。GitHubやBacklogなどのツールを活用し、透明性の高い開発を心がけましょう。
4. 段階的なリリース
すべての機能を一度にリリースするのではなく、段階的に公開していくアプローチが有効です。
MVP(最小限の製品)から始める
まずは核となる機能だけを実装し、実際に使ってみます。この段階で以下のことが分かります:
- 本当に必要な機能は何か
- 使い勝手に問題はないか
- 想定していた効果は得られるか
段階的な機能追加
MVPで基本的な価値を確認したら、優先順位に従って機能を追加していきます。各段階で効果を測定し、投資判断を行うことで、無駄な開発を避けられます。
早期のフィードバック収集
早い段階でユーザーに使ってもらい、フィードバックを集めることが重要です。「完璧にしてから公開」ではなく、「60点でも早く公開して改善」という考え方が、結果的に良いシステムを生み出します。
5. 保守・運用の計画
システムは作って終わりではありません。長期的な視点で保守・運用を計画することが重要です。
運用コストの見積もり
開発費用だけでなく、以下の運用コストも考慮に入れます:
- サーバー費用(月額)
- 保守サポート費用(月額)
- 将来的な機能追加費用
ドキュメントの整備
将来の保守・改修を考慮し、以下のドキュメントを整備します:
- システム設計書
- 操作マニュアル
- 運用手順書
- トラブルシューティングガイド
体制の構築
社内で対応するか、開発会社に委託するかを決め、適切な体制を構築します。24時間365日の対応が必要か、平日日中のみで十分かなど、ビジネスの性質に応じて決定します。
これら5つのポイントを押さえることで、フルスクラッチ開発の成功確率は大きく向上します。最後に、これらすべてをサポートする秋霜堂のサービスについてご紹介します。
作業時間削減
システム化を通して時間を生み出し、ビジネスの加速をサポートします。
システム開発が可能に
システム開発のご相談は秋霜堂へ

ここまで、フルスクラッチ開発について詳しく解説してきました。最後に、フルスクラッチ開発を選ぶべきかどうかの判断基準と、秋霜堂がどのようにお客様をサポートできるかをお伝えします。
フルスクラッチ開発の判断基準
フルスクラッチ開発を選択すべきかどうか、以下のチェックリストで確認してみてください。
フルスクラッチ開発が適している場合
✓ 自社独自の業務フローがあり、パッケージソフトでは対応できない
✓ 競合他社との差別化を図りたい
✓ 将来的な事業拡大に合わせて、システムも成長させたい
✓ セキュリティ要件が厳しく、自社基準での開発が必要
✓ 初期投資は大きくても、長期的な効果を重視する
✓ システムを戦略的な武器として活用したい
3つ以上当てはまる場合は、フルスクラッチ開発を積極的に検討する価値があります。
他の選択肢を検討すべき場合
✓ 標準的な機能で十分である
✓ とにかく早く、安くシステムを導入したい
✓ システムは最小限で良く、本業に集中したい
✓ IT投資の予算が限られている
このような場合は、パッケージソフトやSaaSサービスの活用を検討することをお勧めします。
秋霜堂のサポート体制
秋霜堂は、最先端のソフトウェア技術を用いたWebシステムやAI開発に強みを持つエンジニア集団です。特に、フルスクラッチ開発においては、以下のような体制でお客様をサポートします。
1. 初期相談から伴走
「システム化したいけど、何から始めればいいかわからない」という段階から、お気軽にご相談ください。費用感や技術的な実現可能性について、無料でアドバイスいたします。場合によっては、「フルスクラッチよりも他の方法が適している」という正直なご提案をすることもあります。
2. TechBandによる継続的な支援
単なる受託開発ではなく、「システム開発部門」として、お客様のビジネスに深く入り込んでサポートします。開発後も継続的に改善提案を行い、システムとビジネスの成長を共に目指します。
3. 柔軟な開発体制
- 小規模スタート対応:MVP開発なら200万円〜、2ヶ月〜のスピード開発
- 段階的な拡張:成果を確認しながら、必要に応じてチームを拡大
- コスト最適化:フェーズごとに最適な人員配置で、無駄なコストを削減
4. 高い技術力と豊富な実績
- Node.js、React、Next.jsなど最新技術を活用
- AWS、GCPなどクラウドインフラの構築・運用
- アジャイル開発による柔軟な対応
- 業界を問わない幅広い開発実績
最後に
フルスクラッチ開発は、確かに大きな投資ですが、適切に進めれば、ビジネスを大きく飛躍させる武器になります。「市販のソフトでは物足りない」「自社だけの強みを作りたい」とお考えなら、ぜひフルスクラッチ開発を検討してみてください。
秋霜堂は、お客様のビジネスパートナーとして、システム開発を通じて事業の成功に貢献したいと考えています。小さな疑問でも構いません。お気軽にご相談ください。
失敗しないためのシステム開発の考え方と開発パートナー選定チェックリスト

この資料でわかること
こんな方におすすめです
- システム開発を検討しているが、失敗したくない
- 開発パートナーを選定しているが、選び方がわからない
- システム開発の失敗パターンを知っておきたい
作業時間削減
システム化を通して時間を生み出し、ビジネスの加速をサポートします。
システム開発が可能に









