アプリ開発とは?受託会社へ依頼した場合の費用感や期間、流れを解説

アプリの「受託開発」とは、企業が必要とするスマホアプリやWebアプリの開発を自社ではなく専門の開発会社に委託することを指します。自社内に開発リソースやノウハウが不足している場合、外部のプロに依頼するのが一般的な選択肢です。
受託開発では、クライアント企業の要望に基づき、開発会社が要件整理から設計・実装・テスト・納品まで一括して担当します。また、エンジニアを派遣して常駐作業するSES契約とも異なり、受託開発は完成した成果物に対して報酬が支払われる契約形態です(SESはエンジニアの労働時間に対して報酬が発生)。
本記事では、アプリ受託開発の基本から、メリット・デメリット、プロジェクトの流れ、費用感の相場、開発会社の選び方までを発注者の視点でわかりやすく解説します。

目次
失敗しないためのアプリ開発の考え方と開発パートナー選定チェックリスト
.jpeg&w=1080&q=75)
この資料でわかること
こんな方におすすめです
- アプリ開発を検討しているが、失敗したくない
- 開発パートナーを選定しているが、選び方がわからない
- アプリ開発の失敗パターンを知っておきたい
アプリ開発を受託会社に依頼するメリット

アプリ開発を外部の受託会社に依頼することには、多くの利点があります。主なメリットとして
コスト面・品質面・効率面の3つが挙げられます。
開発コストを節約できる
まず、自社でゼロから開発体制を整えるよりコストを抑えられる点です。社内でエンジニアを採用・育成したり、設備投資を行ったりすると、人件費や環境構築費がかさみがちです。一方、受託開発会社に委託すれば必要なタイミングだけ外部の技術リソースを活用できるため、余計な固定費を発生させずに済みます。
実際、中小企業が新規の業務システムを内製しようとすると高額な人件費・設備費がのしかかりますが、受託開発を利用すれば必要な工程だけを外注でき内部コストを削減できます。このように、外注することで初期投資や人件費を節約しやすく、自社の限られた予算を効率的に使えるのが大きなメリットです。
高品質なアプリ開発が可能
次に、経験豊富なプロの開発チームに任せることで高品質なアプリを実現しやすくなります。専門の受託会社は多様なプロジェクト実績や高度な技術知識を持っており、不具合の少ない安定したアプリを期待できます。例えば、業界特有の要件がある場合でも、その分野に強みを持つ開発会社なら的確な提案や設計が可能です。
自社内に専門スキルがないケースでも、外部のプロの知見を借りれば、最新技術の活用やUI/UX面での配慮が行き届いたクオリティの高いアプリ開発ができます。また、受託会社はチーム体制やレビュー体制が整っているため、プロジェクト進行中の課題発見や品質管理も徹底されます。その結果、完成度の高いアプリを納品してもらえる可能性が高まります。
リソースの有効活用
さらに、開発業務を外部に委託することで自社の人的リソースを本来業務に集中させられる点もメリットです。自社でアプリ開発を行う場合、要件定義からプログラミング、テスト、運用保守まで全てに人手と時間を割く必要があります。プロジェクト期間中、本業に支障が出るケースもあるでしょう。
一方、受託開発会社に開発作業を任せれば、社内の人材は自分たちの本業に専念できます。実際、受託開発を活用することで「限られた人材・時間・予算をコア業務に集中できる」という戦略的なメリットが得られると指摘されています。このように、本業リソースを有効活用しつつプロジェクトを進められる点は、企業経営において大きな利点です。
アプリ開発を受託会社に依頼するデメリット・注意点

一方で、アプリ開発を受託会社に任せる際には注意すべきポイントやデメリットも存在します。
事前にリスクを理解し、適切な対策を講じることが大切です。
開発コストが割高になる可能性がある
まず考えられるのは、開発コストが自社開発より割高になる場合がある点です。外注することで追加のマージンや管理コストが上乗せされ、自社で開発するより費用がかかるケースもあります。特に、一度契約した範囲外で要件追加や仕様変更を行うと、別途費用が発生しやすい点に留意しましょう。
請負契約では契約外の作業は基本的に追加費用となり、プロジェクト後半での変更は技術的にも難しく膨大なコスト増につながることがあります。例えばテスト段階での大幅な仕様変更は、システム全体に影響し再実装に多大なコストが発生する可能性があります。したがって、受託開発では当初の要件定義を綿密に行い、追加コストのリスクを抑える計画が重要です。
自社にノウハウが蓄積されない
次に、自社外で開発を完結させる分、開発ノウハウが社内に蓄積されないデメリットがあります。アウトソーシングでは専門業者に任せきりになるため、社内エンジニアが開発プロセスに関与できず技術スキルを習得する機会が少なくなります。その結果、将来的に自社で開発力を高めたいと考えても、経験や知見が社内に残らないために、自社内でのシステム開発が難航する恐れもあります。
実際、アウトソーシング導入企業では「委託業務に関するノウハウが社内にたまりにくい」という指摘があります。この課題に対しては、発注側の担当者が開発プロジェクトの全体像を把握し、定期的にベンダーと情報共有することで一定の知識移転を図ることが推奨されています。受託開発を利用しつつも、社内に最低限の技術知見をストックする工夫が必要です。
外注先とのコミュニケーションリスク
また、外注先とのコミュニケーションにも注意が必要です。受託開発ではクライアントと開発会社の間で細やかな意思疎通が不可欠とされます。要件の伝達が曖昧なままだと、開発側が独自解釈で進めてしまい、納品物が意図とズレるケースも少なくありません。
さらに、進捗報告が滞ると問題発見が遅れ、納期遅延や品質低下につながるリスクも高まります。そのため、プロジェクトを円滑に進めるには担当窓口を明確にし、定期的な打ち合わせや書面確認を徹底することが大切です。受託開発成功の鍵は技術力だけでなく、綿密なコミュニケーション体制の構築にあると言えるでしょう。
実務上も、例えば週次ミーティングやチャットツールでの密な連絡を取り、認識齟齬を早期に解消する努力が求められます。外注先任せにせず、発注側も初期段階から積極的に関与し、双方で認識合わせをしながら進める姿勢が重要です。
情報漏洩のリスク
さらに、外部に開発を委託する以上、機密情報の漏洩リスクも伴います。プロジェクト遂行のために自社の業務データや顧客情報を開発会社と共有する必要がありますが、その情報管理が万全でないと重要データが流出する恐れがあります。
特に、開発会社がさらに別の協力会社へ業務を再委託している場合、情報管理の実態が把握しづらくリスクが高まります。実際、「信頼していた外注先から重要データが漏洩した」という事例も考えられます。このリスクに対しては、契約時に秘密保持契約(NDA)を締結したり、外注先の再委託状況やセキュリティポリシーを事前に確認することが不可欠です。
万が一情報漏洩が発生すると企業の信用失墜や損害賠償など重大な事態に発展しかねません。したがって、セキュリティ対策を十分講じた開発会社を選定し、契約上も情報保護の取り決めを明確にしておくことが重要です。
以上のようなデメリットを踏まえ、受託開発を利用する際は事前準備とリスク対策をしっかり行いましょう。注意点を把握した上で、デメリットを補える体制づくりや発注計画を立てることが成功のポイントです。
アプリ開発を受託会社へ依頼する際の流れ・手順

では、実際にアプリ開発を受託会社へ依頼する場合、どのような手順で進めていけば良いのでしょうか。ここでは、一般的な開発プロジェクトの流れをステップごとに説明します。
開発するアプリの企画・要件定義
まずは自社内でアプリの企画立案と要件定義を行うフェーズです。開発を成功させるには、発注側が自社のニーズや目的を明確にすることが出発点となります。具体的には、アプリで解決したい課題やターゲットユーザー、提供したい機能を社内で洗い出し、実現したいことの全体像を共有しましょう。
どの業務を効率化したいのか、ユーザーにどんな価値を提供したいのかを整理し、それに合った開発方針を検討します。この段階で可能であれば企画書や要件定義書を作成し、求める機能一覧・画面イメージ・予算や希望納期などもまとめておくとベターです。口頭の説明だけでは認識ズレが起きやすいため、資料に落とし込んでおくことで後の工程がスムーズになります。
なお、この準備段階で社内の関係者間で要件に抜け漏れがないか確認し、優先順位も付けておくと良いでしょう。十分な企画・要件整理は、後々の仕様変更や認識違いによる手戻りを減らすカギとなります。
開発会社の選定・見積もり依頼
要件が固まったら、次に外注先の開発会社を選定し見積もりを依頼します。まずは自社のプロジェクトに合った候補企業をリストアップしましょう。開発会社ごとに得意分野や実績が異なるため、例えば業界知識が豊富な会社や希望するアプリ種別に強い会社を優先的に検討します。
過去に似たようなアプリを手掛けた実績が豊富な会社であれば、要件理解が早く提案力も高い傾向にあります。候補が絞れたら、各社にRFP(提案依頼書)や要件資料を送付し、見積もりを作成してもらいます。複数社から見積もりを取ることで、費用や提案内容を比較検討しやすくなります。
価格だけでなく、見積内訳や対応範囲をしっかり把握することが重要です。例えば、A社は○○万円でテスト・保守まで含むが、B社は安価だがテスト工程は別費用、といった違いもあり得ます。したがって、単純な金額比較ではなく各社の対応内容と費用のバランスを確認しましょう。
またこの段階で、開発範囲(どこまで外注するか)も明確にしておくことが大切です。例えば「基本設計からリリースまで委託し、業務テストは自社で実施」など、自社と外注先の役割分担を決めておくと後々のトラブル防止につながります。
契約締結とプロジェクト開始
発注先の開発会社が決まったら、見積もり内容や提案をもとに正式な契約を結び、プロジェクトを開始します。受託開発では一般的に請負契約(完成責任を伴う契約)が結ばれるケースが多く、契約書には納品物の範囲・納期・検収基準・支払い条件などが明記されます。
契約前に不明点があれば必ず確認し、認識合わせをしておきましょう。契約締結後、開発会社との間でキックオフミーティングを行い、今後の進め方や基本スケジュールを共有します。例えば、定例会議の頻度や連絡方法(メール、チャットツールなど)をこの時点で取り決めておくと良いでしょう。「担当窓口は誰で、週次報告はどう行うか」などをあらかじめ合意しておくことで、開発中のコミュニケーションを円滑にできます。
ここからプロジェクトが本格始動するので、発注者側も体制を整え責任者を配置し、開発会社と二人三脚で進める準備を整えましょう。なお、契約形態によって責任範囲や進め方が異なる点も念頭に置いてください(請負契約では成果物完成が責任範囲、準委任契約では労務提供が中心など)。契約内容に沿った進行管理と信頼関係の構築が、プロジェクト成功の土台となります。
アプリ設計・開発(実装)フェーズ
契約後、いよいよ詳細設計と実装(プログラミング)フェーズに入ります。まず開発会社は要件定義をもとに、画面レイアウトやデータベース設計、API仕様などを詰めた詳細設計書を作成します。発注者側も設計内容のレビューに参加し、業務フローに沿った仕様になっているか確認しましょう。
例えば、販売管理システムなら「受注登録画面でどの項目を入力し、在庫管理とどう連携するか」などを図で示し合意します。設計が固まった部分から順次プログラミング実装が開始されます。開発手法としては、ウォーターフォール型(工程を順番に進める方法)かアジャイル型(短いサイクルで反復開発する方法)か、プロジェクトの性質によって採用されます。
近年ではアジャイル開発を取り入れるケースも増えており、秋霜堂でも1~2週間ごとのスプリントで迅速に開発を進める体制を基本としています。いずれの場合も、開発中は定期的な進捗報告やレビューを実施することが重要です。週次の進捗会議を開いて作業の遅延や課題を早期に共有し、仕様変更の要否も適宜判断します。発注者側もレビューやテストに協力し、認識のズレをその都度修正していくことで完成物の品質を高められます。
なお、開発途中に仕様変更が発生した場合は、契約形態によって対応可否や費用発生が異なります。請負契約では原則契約範囲外の変更は難しいため、変更内容の重要度を見極め慎重に判断しましょう(柔軟な対応が必要なら準委任契約へ切り替える選択もあります)。いずれにせよ、綿密な連携とドキュメント管理を行いながら実装フェーズを進めることで、後工程での手戻りを最小限に抑えることができます。
テストの実施・ストア申請とリリース
実装が完了したら、納品前に各種テストを入念に行います。開発会社側での単体テスト・結合テスト(ユニットテストや統合テスト)を経て、システム全体が要件どおり動作するかを検証します。並行して、発注者側でも受け入れテスト(UAT)を実施し、自社の業務シナリオに沿って問題がないか確認します。
例えば、業務画面の挙動や帳票出力が仕様書通りか、複数部署で試験的に操作してみて不具合が出ないか検証します。不具合や要調整事項が見つかれば開発会社に修正を依頼し、品質基準を満たすまでテストと改修を繰り返します。納品物の検収条件に照らし、全ての必須項目をクリアしたら、いよいよリリース工程に移ります。
スマートフォンアプリの場合は、App Store(iOS)やGoogle Playストア(Android)へのストア申請手続きが必要です。ストア申請時には、アプリのビルド提出に加え、スクリーンショット画像や説明文、プライバシーポリシーURLなどプロモーション情報の準備も求められます。
特にAppleの審査はガイドラインが厳格で、申請から承認まで時間がかかる傾向があります。実際、ある開発者の報告によれば新規iOSアプリの審査にはスムーズでも約2週間程度、アップデートでも1週間ほど要したケースがあるようです。もちろん内容によって早まることもありますが、リジェクト(却下)され再申請となるとさらに日数が延びます。
一方、Androidの審査期間は比較的短く24~48時間程度で完了する場合が多いものの、機能や内容によっては最大7日ほどかかることもあります。このようにプラットフォームごとに申請プロセスが異なるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。Appleのガイドライン遵守や事前テストフライトによる確認など、リジェクトを避ける工夫も行いましょう。
審査が無事通過すればストア上でアプリが公開され、ユーザーがダウンロードできるようになります。Webアプリの場合はサーバーへ本番デプロイ(本番環境へのシステム配置)を行い、所定のURLでサービス提供を開始します。リリース直後はシステムが安定稼働するか監視し、問題発生時には即座に対応できるよう体制を整えておきます。
リリース後の運用・保守
アプリ公開後も、運用・保守フェーズが続きます。リリース直後はユーザーからのフィードバックや不具合報告を収集し、必要に応じて迅速に修正アップデートを行います。特に一般ユーザー向けアプリの場合、初期バージョンでのユーザー評価が今後の利用継続に影響するため、不具合の早期発見・解消が重要です。
開発会社と保守契約を結んでおけば、ログ監視やエラートラッキングにより問題を未然に検知し、バグ修正版のリリースをスムーズに実施できます。また、スマホアプリの場合はOSのアップデートやストアガイドラインの変更にも継続対応が必要です。定期的にiOS/Androidの最新動向をチェックし、互換性を保つための改修を行います。
さらに、ユーザー要望や市場の反応を踏まえて機能追加や改善を検討する段階でも、引き続き開発会社がサポートしてくれると安心です。秋霜堂のように運用・保守フェーズまで継続サポート可能な会社であれば、プロダクトの立ち上げから安定稼働・成長まで一貫して伴走してもらえます。運用開始後も発注者と開発会社が二人三脚でアプリを育てていくことで、ユーザー満足度の向上や事業価値の最大化につながります。
アプリ開発にかかる費用・期間の目安

アプリ開発にかかる費用や期間は、その内容によって大きく変動します。ここでは一般的な相場観や目安を解説します。
アプリ開発費用の相場と変動要因
アプリ開発費用は、開発方式や機能の複雑さ、対応プラットフォームによって幅があります。小規模でシンプルなアプリなら数十万円程度で済む場合もありますが、本格的なシステム連携や高機能を備えたアプリでは数百万円〜数千万円規模になることも珍しくありません。例えば、国内のある調査によれば開発方式別の費用相場は以下のような傾向があります。
- ノーコード開発:プログラミング不要のツールを使う方法で、費用は数万円〜数百万円程度と安価。ただし機能カスタマイズ性は低め。
- ハイブリッド開発:ノーコードとフルスクラッチの中間的手法で、費用は概ね150万円〜から。独自機能もある程度実現可能で、期間も比較的短く2ヶ月〜が目安。
- フルスクラッチ開発:ゼロからすべて開発する方法で、費用は1,000万円以上と高額になりがち。ただ自由度が高く高度な要件にも対応できる。
このように、開発手法の違いだけでも費用感は大きく変わります。また、求められる非機能要件(セキュリティ強度や可用性など)や外部システム連携の有無によっても工数は増減します。例えば、決済システムや独自のバックエンドとの連携が必要な場合、その実装と検証に追加コストが発生します。見積もりを依頼する際は、機能要件だけでなくこうした変動要因も含めて相談し、適切な予算設定につなげることが大切です。
アプリ種別ごとの費用感の違い
アプリの種類や用途によっても開発費用のレンジは大きく異なります。いくつか代表的なアプリ種別を例にとり、その費用感を見てみましょう。
- マッチングアプリ(例:フリマアプリや出会い系サービス等):ユーザー登録・検索・メッセージ機能など多数の機能が必要になるため、開発費用は数百万円~1000万円程度と高額になりやすいと言われます。例えば、基本的な機能だけのシンプル版でも400~600万円、機能充実版では700万~1500万円程度が相場との事例もあります。それだけ要件が多岐にわたるためです。
- 業務支援アプリ(例:営業支援や在庫管理など社内利用システム):機能は業務特化であるものの、企業毎に要件が異なりオーダーメイド性が高いため300万~600万円程度が一般的な相場です。既存テンプレートでは対応しづらい複雑な業務フローだと費用幅がさらに広がります。
- ECアプリ(ネット通販アプリ):商品検索・カート・決済・レビューなど多彩な機能を伴うため、1500万円以上かかるケースもあります。シンプルなカタログ閲覧程度ならもう少し抑えられますが、本格ECではサーバー側の大規模構築が必要なためです。
- コンテンツ配信アプリ(動画/音楽ストリーミング等):DRM対応や大容量配信インフラが必要となり、開発費用数千万円規模のプロジェクトになることもあります。例えばNetflixのような高度な機能は別格としても、基本的な動画配信でもプレイヤー機能やサーバー設計に工数がかかります。
- ポータルサイト系アプリ(ニュース・地域情報など多機能ポータル):機能統合度によって費用差が大きく、小規模なら300万円以内、大規模なら1000万円以上になる例も報告されています。広告管理や会員機能を組み込むと費用が一気に跳ね上がる傾向です。
このように、用途に応じた相場を把握しておくと予算計画の参考になります。例えば「フリマアプリを開発したい」と思ったら、同種のサービス事例からおおよその費用イメージを掴んでおくと良いでしょう。
弊社ブログでも「フリマアプリを開発するには?基礎的な知識や機能、流れを紹介」や「ECサイトを開発する5つの方法!手順や成功のポイント・注意点を解説」といった記事で各種システム別のポイントを解説していますので、ぜひ参考にしてください。
開発期間とスケジュール管理のポイント
アプリ開発にかかる期間も、規模や要件で様々ですが、企業向けアプリの場合おおむね4~6か月程度がひとつの目安になります。中規模のWebシステム開発では、2~6ヶ月・4~10人月程度というのが一般的な相場観で、これに照らすと複数機能を備えたビジネスアプリでも半年弱の期間でリリース可能なケースが多いでしょう。
もちろん、機能数が少ない小規模アプリであれば1~2ヶ月程度で開発できる場合もありますし、大規模で複雑なアプリでは6ヶ月~1年以上かかるプロジェクトも存在します。たとえば企業の基幹業務に関わるようなシステムだと6ヶ月~1年、さらに全社的な大型システムになると1年以上を要することもあります。
スケジュール管理のポイントとしては、余裕を持った計画を立てることです。開発そのものの工数に加えて、要件定義や設計の調整期間、テスト期間、そして前述したストア申請期間なども考慮します。特にiOSアプリの審査には不確定要素もあるため、リリース希望日の1〜2ヶ月前には申請手続きを完了できるよう逆算すると安心です。
また、開発途中での仕様変更や追加要望への対応時間も見込んでおきましょう。実務的には、マイルストーン(節目)を設定し、各フェーズの完了目標日を明確にして進捗管理すると効果的です。週次・月次でプランと実績を見比べ、遅延が発生しそうなら早めに体制増強やスコープ調整を検討します。
納期ありきで進める中でも、品質確保のためのテスト期間は十分確保することが重要です。計画段階でバッファ(予備期間)を設けておくと、想定外のトラブルが起きても慌てず対処できます。要は「急がば回れ」で、余裕あるスケジュールが結果的にプロジェクト全体の成功につながるでしょう。
失敗しないためのアプリ開発の考え方と開発パートナー選定チェックリスト
.jpeg&w=1080&q=75)
この資料でわかること
こんな方におすすめです
- アプリ開発を検討しているが、失敗したくない
- 開発パートナーを選定しているが、選び方がわからない
- アプリ開発の失敗パターンを知っておきたい
アプリ開発の外注先を選ぶ際のポイント

次に、アプリ開発を外部に委託する際の開発会社選びのポイントについて解説します。発注先の選定は、開発の成否を左右する重要なステップです。以下の観点をチェックして、安心して任せられるパートナーを見極めましょう。
得意分野や実績の確認
まず注目したいのは、開発会社の得意分野と過去実績です。その会社が自社のプロジェクト内容にマッチした専門性を持っているかを確認しましょう。業界やアプリ種類ごとに要求される知識・技術は異なるため、例えば「物流業界向けシステムが得意な会社」なら物流特有の仕様理解が深く、要件定義から的確な提案が期待できます。同様に「医療系に強い会社」なら医療データの扱いや電子カルテ連携などにも精通しているでしょう。
このように自社の業種・目的に合った専門性を持つ会社を選ぶと、コミュニケーションコストも下がり、開発精度とスピード両面で高い成果を得やすくなります。また、過去の開発実績数や具体的な事例紹介も技術水準を測る指標になります。
同種システムの開発経験が豊富な会社ほどノウハウが蓄積されており、トラブル対応力にも期待できます。「〇〇システムを過去に○件開発」などの実績情報や顧客評価を確認し、信頼できる相手か判断しましょう。
対応範囲とサポート体制の充実
次に、候補会社がどこまで開発工程を一括対応できるか、そのサポート体制も重要なポイントです。要件定義から設計・開発・テスト・リリース・保守までワンストップで担える会社であれば、フェーズごとに別ベンダーへ引き継ぐ必要がなく、コミュニケーションロスや管理コストを減らせます。秋霜堂ではヒアリングから運用開始まで全工程を一貫対応しており、フェーズ間の断絶なくスムーズに進行できる体制を整えています。
一方、開発会社によっては「開発まで対応するが運用保守は別契約」など範囲が限定的な場合もあります。リリース後のサポートをどこまで望むかによって、適したパートナーは変わるでしょう。長期的な運用や追加開発も見据えるなら、運用フェーズまで継続サポート可能な会社を選ぶと安心です。また技術スタッフの対応範囲も確認しましょう。
自社が希望するプラットフォーム(iOS/Android、Webなど)や使用したい技術に対応できない会社だと、計画通りの開発ができなくなります。複数OS対応アプリであれば両プラットフォームの実績があるか、最新のフレームワークに精通しているか、といった点もチェックします。
コミュニケーションのしやすさ
コミュニケーションの質も開発会社選びでは見逃せません。どんなに技術力が高くても、意思疎通が円滑でないとプロジェクト全体のスムーズさに支障をきたします。具体的には、問い合わせに対するレスポンスの速さや、説明の分かりやすさ、担当者の人柄などが評価ポイントになります。問い合わせ段階でメールの返信に何日もかかるようでは、開発中の対応にも不安が残ります。
できれば初期の打ち合わせで担当エンジニアとも直接話し、専門用語をかみ砕いて説明してくれるか、こちらの要望をきちんとヒアリングしてくれるかを感じ取りましょう。また、営業担当しかやりとりできない会社だと、細かな仕様変更への対応が遅れがちです。秋霜堂では営業窓口を現場経験豊富なエンジニアが担当するため、初期相談から技術的な課題もすぐ解決できる強みがあります。
さらに、納品後の保守サポート体制も確認しましょう。不具合対応や問い合わせ対応が迅速か、土日対応は可能か、といった姿勢は運用フェーズで重要になります。信頼して相談できる会社を選べば、開発中に想定外の問題が起きても柔軟に対処しやすく、発注者側のストレスも軽減されます。
費用・納期と品質のバランス
提示された費用や納期が適切かどうかも重要な見極めポイントです。他社に比べて極端に安すぎる見積もりには注意が必要です。安価に引かれて依頼したものの、実際には品質や対応力に問題があり、結果的に不具合修正でコスト超過…というケースもあり得ます。
例えば、A社は300万円でテストや保守まで含むが、B社は200万円だがテストやサポートは別費用、といった場合、単純な金額だけで判断すると後から追加費用が発生しトータルでは高くつくことがあります。見積もりの内訳をよく確認し、各工程に十分な工数が割り当てられているか、技術難易度に見合った費用感かを判断しましょう。
逆に、見積もりが不明瞭で一式金額のみ提示の場合も要注意です。その際は根拠を尋ね、納得できる説明が得られる会社を選びましょう。納期についても、あまりに短すぎる提案にはリスクがあります。無理なスケジュールは品質低下や納品遅延につながりかねません。
複数社の見積もりを比較しつつ、費用・納期と期待品質のバランスが取れているかを総合的に判断することが大切です。見積もり比較にあたっては最低でも2~3社以上から取り、極端に開きがある項目は質問してみると良いでしょう。
セキュリティと契約面での安心感
最後に、セキュリティ対策や契約面の信頼性も欠かせません。前述した情報漏洩リスクに関連しますが、NDAの締結に快く応じる会社か、社員の情報セキュリティ教育を実施しているか、といった点はチェックしておきましょう。
また、開発会社の体制として下請け構造になっていないかも確認事項です。実際の開発をさらに別企業へ丸投げするような場合、自社からの要望伝達が間接的になり、品質管理も行き届かない懸念があります。可能なら「自社内で開発を完結していますか?」などヒアリングし、責任の所在が明確な会社を選びましょう。
契約書の取り交わしも重要で、成果物の仕様や検収条件があいまいなままだとトラブルのもとです。契約段階で不安が残る対応をする会社より、法務面でも誠実で丁寧に契約事項を説明してくれる会社は信頼度が高いと言えます。
さらに、災害対策やソースコードのバックアップ管理などリスク対応力も確認すると安心です。総じて、情報管理や契約遵守の姿勢がしっかりしている会社を選ぶことで、後々の安心感が違います。発注パートナーとは長期的なお付き合いになるケースも多いため、「技術力+人間的信頼性」で総合評価することが大切です。
アプリ開発の費用を抑えるコツ
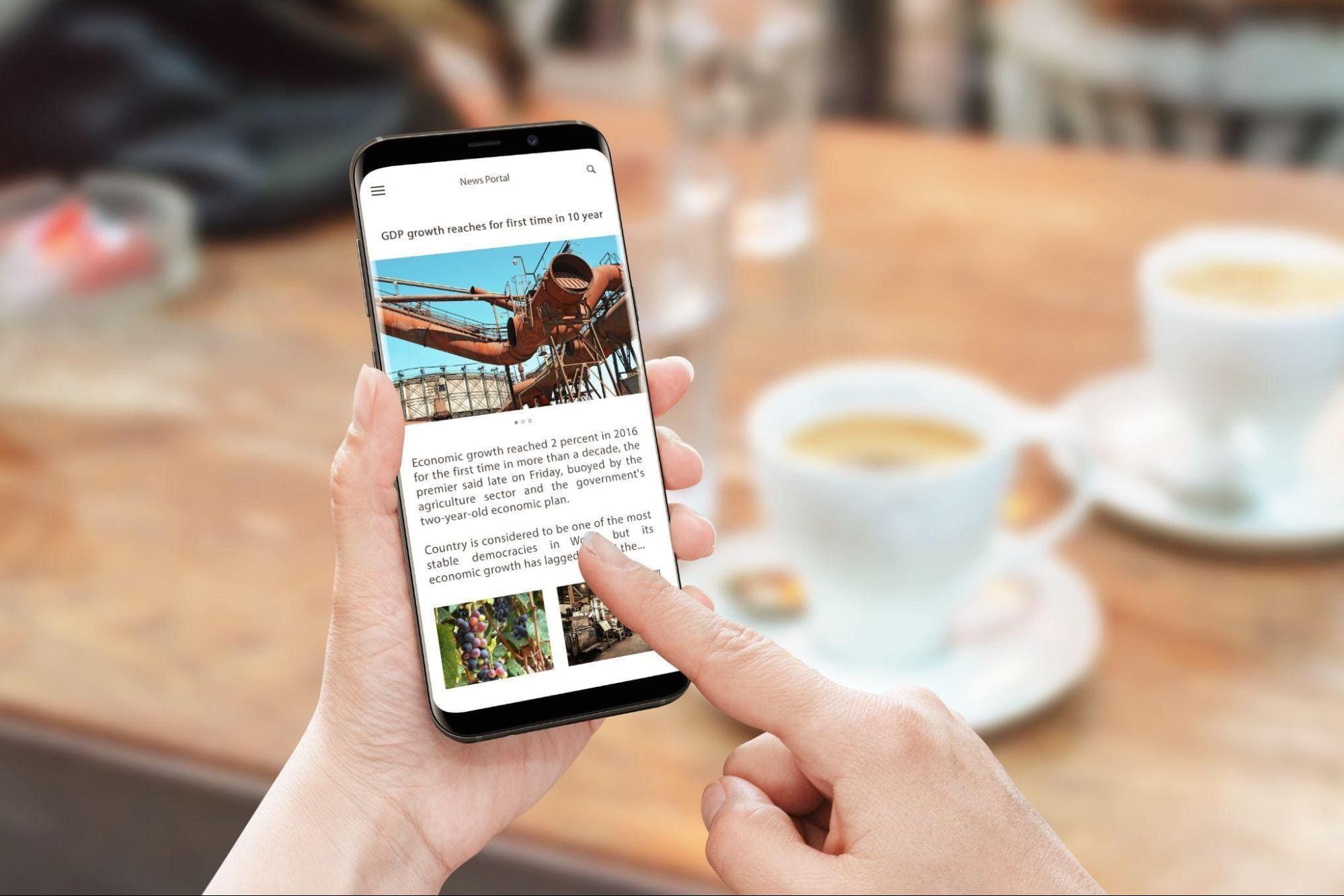
アプリ開発はどうしても高額になりがちですが、工夫次第で費用を抑えることも可能です。ここでは予算削減に役立ついくつかのコツを紹介します。
機能の取捨選択でコスト最適化
まず重要なのは、アプリに実装する機能の優先順位を明確にし、必要な機能に絞り込むことです。欲張ってあれもこれもと詰め込むと、開発期間も費用も膨らんでしまいます。そこで、MVP(Minimum Viable Product)の考え方を取り入れてみましょう。
MVP開発とは「最小限の核心機能だけを備えた製品をまずリリースし、ユーザーの反応を見ながら改善していく」手法で、無駄な機能や過剰な開発コストを抑えるのに有効です。例えば本来3ヶ月かかる開発を、コア機能だけなら1ヶ月でリリースしてしまい、その段階で得られたデータをもとに次の開発に投資する、といった段階的アプローチが可能です。
これにより初期投資を抑えつつROI(投資対効果)を最大化できるとされています。実際、MVP開発を活用すればフル機能実装時に比べ開発期間や外注コストを大幅圧縮できるケースが報告されています。
したがって、「最初のリリースでは核となる○○機能だけ提供し、その他の△△機能は次期バージョンで検討」といったように機能を取捨選択することで、開発コストの最適化が図れます。ユーザー満足度とのバランスを見極めつつ、実装範囲を絞り込むのがコツです。
なお、MVP開発の基本や進め方については、当社ブログ記事『MVP開発で始めるシステム開発!失敗リスクを抑えるWebシステム構築の第一歩』でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
一部工程の自社対応で費用削減
次に、開発工程の中で自社で対応可能な部分は自社対応することで外注コストを削減する方法があります。例えば、最終段階の受け入れテストやストア申請手続きは自社で行うことも可能です。受け入れテスト(UAT)は自社業務に即した観点で行う必要があるため、むしろ自社メンバーが主体となった方が網羅的に検証できる場合もあります。
その分、テストケース作成や実施工数を外注しなければ費用を浮かせられます。また、App StoreやGoogle Playへの申請作業も、開発会社に任せると手数料が発生することがあります。これを自社で担当者が学んで対応すればコストカットにつながるでしょう(iOS開発者登録料など必須の実費はありますが、申請代行費を省けます)。
さらに、プロジェクト管理や進捗監視を自社PMが担うことで、開発会社側のPM工数分を減額してもらうケースもあります。ただし、自社対応部分が増えると社内負荷も高まるため、社内リソースとの相談になります。無理のない範囲で「ここは自社でやるので、その分見積もりから外してください」と交渉すると良いでしょう。自社が関与することでスケジュール調整の柔軟性も増し、結果的に効率化できる面もあります。
開発手法・ツールの見直し
開発そのものの手法やツール選定を工夫するのも費用削減のポイントです。上述のノーコード開発や、既存プラットフォームを活用した開発はその代表例です。例えば、ノーコードツールを使えばプログラミング作業が不要になる分、費用を大幅に削減できます。
ある調査ではノーコード型の費用相場は数万円〜最大500万円程度とされ、ゼロからエンジニアが書く場合に比べてコストを大きく抑えられるメリットがあるとされています。ただし独自機能や複雑なシステム連携が必要な場合、ノーコードでは対応できないケースが多い点に注意が必要です。
そこで、主要部分は既存プラットフォーム(例えばモバイルバックエンドサービスやCMSなど)を利用し、不足部分だけカスタマイズ開発する「ハイブリッド型」も有効です。ハイブリッド型ならフルスクラッチより費用を抑えつつ、ある程度の独自機能・デザインも実現できます。
また、オープンソースの活用や社内にある既存システム流用なども検討しましょう。ゼロから作らず流用できるものは流用することで工数を減らせます。いずれの場合も、コストとカスタマイズ性のトレードオフを踏まえて判断することが重要です。安価だけれど柔軟性が低い方法が自社の目的に合うのか、見極めた上で最適な開発アプローチを選択しましょう。
補助金や助成金の活用
国や自治体のIT導入補助金や各種助成金を活用するのも賢い方法です。日本国内では、中小企業向けにITツール導入費用の一部を支援する制度が多数用意されています。代表的なものに「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」、「事業再構築補助金」「小規模事業者持続化補助金」などがあります。
例えば、ものづくり補助金(一般型)では100万円〜1,000万円の補助額で、中小企業は費用の1/2(小規模事業者なら2/3)を補助してもらえる枠組みがあります。条件を満たせば、最大1,000万円の補助を受けられるケースもあり、実際にシステム開発プロジェクトで多数の採択実績があります。IT導入補助金も、ソフトウェア導入費用の1/2(特定条件で2/3)を補助する制度で、数百万円規模まで支援が得られます。
こうした制度を利用すれば、自己負担を大きく軽減して質の高いアプリ開発に取り組むことが可能です。注意点としては補助金は後払い(事業完了後の交付)であることや、申請に事業計画書など手間がかかることです。
しかし補助金申請代行サービスなどもありますので、時間がなければ専門家に相談するのも一つの手です。補助金情報は毎年内容が変わるため、2025年現在の最新情報をチェックし、自社が該当しそうなものには積極的にエントリーしてみましょう。
複数社見積もり・交渉による調整
最後に、複数の開発会社から見積もりを取り比較・交渉することで、より最適なコストと内容で契約できる可能性が高まります。前述の通り、1社だけの見積もりではそれが高いのか安いのか判断しづらいため、手間でも相見積もりは基本と考えましょう。
複数社の提案を比較する中で「○○機能はA社ではオプション費用だがB社では標準対応内」といった発見があり、交渉次第で条件を揃えられることもあります。例えばA社に「他社ではこの部分まで含めた価格でした」と伝えれば、歩み寄ってくれるケースもあります。開発会社側も競合状況が分かれば、できる限り予算に合わせようと努力してくれることが多いです。もちろん極端な値下げ交渉は関係悪化に繋がるので慎重に行う必要がありますが、スコープや工程の調整による費用圧縮提案など建設的な交渉は歓迎されるでしょう。
「○○のテストは当社でやるので、その分コスト調整いただけますか?」といった具体的な相談も効果的です。複数社の見積もりを取るプロセス自体が自社の要件を再整理する機会にもなり、発注内容の漏れ防止にも役立ちます。総じて、見積もり比較と適切な交渉によって、納得感の高いコストでアプリ開発を進めやすくなります。
作業時間削減
システム化を通して時間を生み出し、ビジネスの加速をサポートします。
システム開発が可能に
秋霜堂株式会社の開発事例

秋霜堂株式会社(TechBandサービス)の開発事例をいくつかご紹介します。当社では多様な業種・用途のシステム開発を手掛けており、その中から代表的な成功事例を抜粋します。
事例① アパレル企業 – 品質管理システムの改善・保守
あるアパレルメーカーから、既存の品質管理システムに関するご相談を受けました。課題は「画面表示に時間がかかる」「自動バックアップができない」「動作が不安定」といった点で、新任担当者の着任を機にインフラ刷新とシステム全体の安定化を図りたいというニーズでした。
開発対応: 当社では既存インフラの再設計・構築と、アプリケーションの軽量化・機能強化を実施しました。2〜3名のチーム体制で約4ヶ月かけて段階的にシステムを移行し、その後保守運用フェーズでは2年以上にわたり継続的な改善支援を行っています。
成果: 画面の表示スピードが飛躍的に向上し、現場ユーザーの満足度が大幅アップしました。また自動バックアップ機能の導入でデータ消失リスクを低減し、システムの安定稼働と長期運用体制を構築できています。
事例② 広告会社 – SNSマーケティングシステムの新規開発
SNSを活用したマーケティング支援を行う広告企業からは、「業界に前例のない独自プロダクトを開発したい」とのご依頼がありました。企画段階から当社エンジニアが伴走し、ゼロからの新規サービス立ち上げに取り組みました。
開発対応: 初期フェーズではエンジニア2名で市場調査や技術PoC(実現可能性検証)を行いつつ、プロトタイプ開発を並行。サービスの有用性が確認された段階で開発チームを6〜8名に拡大し、約13ヶ月間のアジャイル開発で本格システムを構築しました。リリース後はクライアント社内エンジニアへの引き継ぎ支援も実施しました。
成果: 業界初のSNSマーケティング支援ツールを無事リリースし、サービスイン。アイデア出しから運用・社内移管までをワンストップで支援し、クライアント企業の新規事業立ち上げを成功に導きました。また実証・改善を繰り返す開発体制により、市場投入から早期にプロダクトマーケットフィット(市場適合)を実現できました。
事例③ BtoBサービス業 – 動画校正システムの新規開発
動画制作会社からは、制作工程で発生していた動画校正・フィードバック作業の煩雑さを解消するための社内ツール開発をご依頼いただきました。
開発対応: 要件が固まりきっていない部分も多かったため、エンジニア1〜2名でアジャイル開発を実施しました。開発中は毎週のミーティングやチャットでクライアントと密に連携し、業務理解を深めながら設計・実装・微調整を繰り返しました。その結果、約6ヶ月で実用性の高いシステムを完成させました。
成果: 従来は手作業が多かった動画校正プロセスを大幅に効率化し、少人数のチームでもスピーディかつ柔軟に対応可能なワークフローを実現しました。システム完成後も継続的に改善提案を行い、運用定着を支援しています。
以上のように、秋霜堂では既存システムの改善から新規サービス開発まで幅広く対応し、短納期・高品質な成果を提供してきた実績があります。それでは、当社のサービス強みについてさらに詳しくご紹介します。
秋霜堂のアプリ開発サービスの強み

秋霜堂株式会社(自社サービス名:TechBand)のアプリ開発サービスには、他社にはない独自の強みがあります。私たちは単なる「受託開発会社」に留まらず、お客様企業の“システム開発部門”として内製レベルで伴走支援することを目指しています。その主な特徴を順に解説します。
エンジニアによる直接ヒアリングと技術提案
秋霜堂では、初期ヒアリングの段階からエンジニアが直接対応する体制をとっています。営業担当者ではなく開発現場を知るエンジニアが窓口になることで、ヒアリングの場で出た技術的疑問や課題をその場で即座に検討・解決できます。「これは実現可能か?」「別のアプローチはないか?」といった高度な相談にもリアルタイムで回答できるため、要件定義がスムーズに進みます。また、エンジニア視点で潜在的な課題を引き出し、ビジネス目線での企画提案まで踏み込めるのも強みです。
例えば「本当にシステム化が必要か」「優先すべき機能は何か」といった根本的な問いから一緒に考え、最適な解決策を提案します。初期の簡易見積もりや技術アドバイスも即日対応し、必要に応じてその日のうちに概算費用や方式提案をご提示できます。さらに、土日や夜間のご連絡にもエンジニアが迅速対応します。このように、専門技術者がお客様と直接対話し課題解決に当たることで、コミュニケーションロスを最小限に抑え、プロジェクトの立ち上がりを加速します。
アジャイル型の柔軟な開発体制
当社は1週間単位のアジャイル開発サイクルでプロジェクトを進めるのを基本としています。専属の開発チームを編成し、短期間のスプリントを回すことで、常に最新の進捗を共有しながら開発を進行します。この体制により、要件の微調整や仕様変更にも柔軟かつスピーディーに対応できます。
例えば、開発途中で新しいアイデアが出てきた場合でも、次のスプリントで試験的に実装してみる、といった素早いフィードバックサイクルが可能です。実際、秋霜堂では状況に応じてエンジニア人員を増減するなどリソース調整も機敏に行い、納期短縮やコスト削減のニーズにも柔軟に応えています。また、お客様とは週次で進捗デモやレビューを実施し、「作ってみたらイメージと違った」といったズレを早期に修正します。
こうしたアジャイルな進め方のおかげで、スピード感と確実性を両立した開発が可能となっています。仕様変更や追加機能が発生しても追加見積もりは不要で、スケジュール調整内で極力対応するポリシーを掲げている点も、お客様に喜ばれているポイントです(当社では「要件変更=すぐ追加請求」ではなく、まず工程調整で吸収できないかを検討します)。
密なコミュニケーションと透明な進行管理
秋霜堂ではコミュニケーションの徹底と進行状況の透明化に強いこだわりがあります。認識ズレを防ぐため、プロジェクト開始時からお客様との情報共有を密に行います。オンラインMTGやチャットツールを活用し、細かな質問や確認事項も随時やりとりして、モヤモヤを残しません。
特に開発中は毎週の定例ミーティングに加え、日次の進捗共有や課題管理を実施します。お客様にはJiraやBacklogといったプロジェクト管理ツール上で進行状況をリアルタイム確認いただける環境を整え、常に「今どこまで進んでいるか」「課題は何か」が見える化されています。これにより、発注者側で不安に感じることなくプロジェクトをお任せいただけます。
高い技術力とマーケティング視点の両立
TechBandの開発チームは、採用通過率5%という厳選された精鋭エンジニアで構成されており、技術力の高さに定評があります。最新のフレームワークやクラウド技術にも精通し、難易度の高い実装やパフォーマンスチューニングにも即対応可能です。
私たちは技術力に加えてマーケティング視点を重視した開発提案を行える点も特徴です。単に言われたものを作るのではなく、「その機能はユーザー体験的にどうか」「ビジネス上の価値向上につながるか」を考え、必要に応じてUI/UX設計の改善提案なども行います。要件ヒアリングの際には事業目標まで伺い、それを達成するために最適なアプリ像を一緒に描きます。
短納期・高品質&迅速なサポート
最後に、短納期・高品質を両立し、かつサポート対応も迅速である点を挙げます。納期遵守はもちろん、当社では「できるだけ早く成果を出す」ことにコミットしています。アジャイル手法により初期リリースまでのリードタイムを極力短縮し、例えば通常3ヶ月かかるものを1.5~2ヶ月程度で提供したケースもあります。短納期でも品質は妥協せず、コードレビューや自動テストを徹底して不具合の混入を防いでいます(当社プロジェクトでは平均して不具合収束期間が短いとの評価を頂いています)。また、サポート対応の速さも強みで、土日含めて何かあればすぐにエンジニアが対処します。メールやチャットの返信も原則即日、内容によっては数時間以内に回答します。リリース後に万一障害が発生した場合も、待機メンバーが即座に原因調査・復旧対応し、お客様への影響を最小限に留めます。
TechBandによるアプリ開発
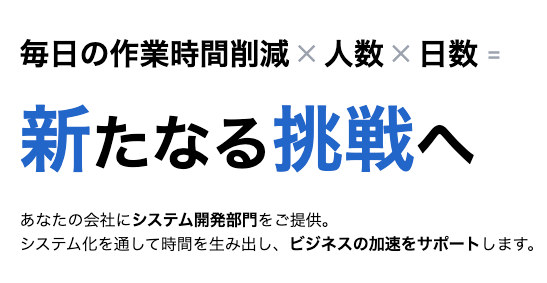
以上、アプリ開発の受託について基本から応用まで解説しました。自社にエンジニアがいない中小企業やスタートアップでも、TechBandのサービスをご利用いただければ、あなたの会社のシステム開発部として寄り添い、スピード感と柔軟性ある開発を実現いたします。
なお、TechBandサービスの詳細は当社サービスページ(TechBand)にてご紹介しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。アプリ開発をご検討中の企業様は、ぜひ秋霜堂株式会社にご相談ください。私たちがパートナーとして伴走し、貴社の事業成功に向けて価値あるプロダクトを共創いたします。
失敗しないためのアプリ開発の考え方と開発パートナー選定チェックリスト
.jpeg&w=1080&q=75)
この資料でわかること
こんな方におすすめです
- アプリ開発を検討しているが、失敗したくない
- 開発パートナーを選定しているが、選び方がわからない
- アプリ開発の失敗パターンを知っておきたい
作業時間削減
システム化を通して時間を生み出し、ビジネスの加速をサポートします。
システム開発が可能に









